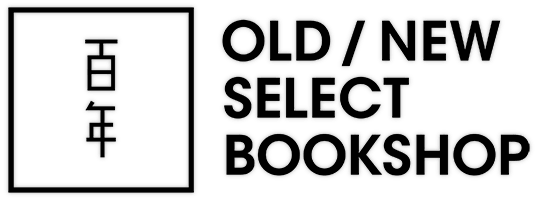百年「と」トークイベント
古谷:これはちょっと関係ないんだけど『パノララ』って連載ですよね。

柴崎:連載です。
古谷:これ凄い伏線はりまくりじゃない。
柴崎:そうですか?
古谷:どれくらい書く前に考えたのかな、と思ったんですけど。
柴崎:まあまあ考えました。笑。
古谷:笑。例えば11章の、初めて木村さんの家族が全員そろって、主人公の田中さんと一緒に食事をする部分なんて、ほぼ全部伏線でできているなぁと思って。
柴崎:そうですね、結構考えましたけど、推理小説や一般に伏線と呼ばれる書き方に比べると、全然伏線じゃないかも。設定?くらいの感じじゃないかと思います。大体は考えていて、最後はこうなって、とか要所・要所は決めていて。あとは書きながら決めていくのですけど。単行本になる時に直したところはあります。伏線って、最初からこうなると決まっているというよりは、書いているうちに伏線になるんですよ。要素が複数あって、後からどれを拾うかみたいなところはあります。まったく意図せず書いたことが、あ、これが使える、と生きてくることもありますし。どこまで意図している伏線かというのはわからない。人の作品でも、この伏線は最初から伏線じゃなかったのではないか、とも思います。絵にしても、最初から構成を作っているのかどうかっていうのとどこまでそれが自分の意図したものかというのはちょっとわからないですよね。
古谷:小説をずっと読んでいて、あれが伏線だったって気が付くと時間がくるっとそこへ戻る感じがするんですよ。ここは前のあれとの繋がりだなみたいな。そういうのは面白い。それが、最後で一日が5回くらい繰り返されるところの感じと結構近いのかな、っていう。
柴崎:伏線で時間がループするというか、読んでいて時間の進み方が変わるみたいな感じは面白いですね。伏線ってそういう役割があるっていうのは、なるほどと思いました。
古谷:ミステリとかではないので、事件解決はしなくてもいい感じなんで、ブイを置いとくとパッと戻るところがある。
柴崎:そのブイがもっといっぱいあって・・・
古谷:あとからどれを拾っていくか、みたいな。
柴崎:そうそう。そういう感じなんです。そんなにすごく整然としていることにこだわらないので、戻り方がきっちりしていない。それは自分の作品だけでなくて、人のものを見ているときも。あんまり整合性とかは気にならない。
ちょっと話が飛ぶんですけど、今度古谷さんに会ったら言おうと思っていた話です。古谷さんも『偽日記』に何度か書いている『マルホランド・ドライブ』や『ロストハイウェイ』の登場人物は、入れ替わるじゃないですか。去年の10月にロサンゼルスに行ったんですよ。そうしたら、もう普通に『マルホランド・ドライブ』だったんですよ。笑。『マルホランド・ドライブ』を映画で見ると、とっても変な・・すごく不条理で、デヴィッド・リンチの頭の中はどうなっているんだと思うんですけれど、ロサンゼルスにいると「リアリズムだったのか」と。普通のロサンゼルスの毎日みたいな感じがすごくして。『マルホランド・ドライブ』を見てロサンゼルスに行っているからそう感じるのかもしれないけど、たぶんそんなに変じゃないです、『マルホランド・ドライブ』は。ハリウッドのメジャーな映画のほうが変なんだと、現地に行ってみて実感して。ロサンゼルスは毎日晴れているんです。毎日空が真っ青で、季節感があまりない。日本だと春夏秋冬にそれぞれ咲いている花ががいっぺんに咲いていて。ズレている奇妙な世界。
古谷:1年間ずっと同じ気候なんですか?
柴崎:多少違いはあるんですけど。紅葉している横で辛夷(こぶし)が咲いているみたいな状態で。ハリウッド映画のハイテンションな感覚は、この毎日が春で快晴みたいな天候から来ていて、とてもクレイジーなものなんじゃないかと。『マルホランド・ドライブ』はむしろ穏やかな感じがします。道を歩いていて、たまたま広い道路の途中にあるマクドナルドに入ったんですね。そこの裏の駐車場の方の出口から出た瞬間に『マルホランド・ドライブ』のダイナーの裏で怖いお婆さんが出てくるところがあるじゃないですか、そことそっくりで、映画の中に今入った、くらいのすごい衝撃だったんですよ。でもその感じって人には伝えられない。例えばそこを写真に撮ってもただのマクドナルドの駐車場です。でも、違う世界とつながった、その異様な感じが強く残っていて。それはさっきの場所が変わると感覚が変わる感じにつながっていると思うんですけど。だから平塚のその平べったい景色も、実はとっても変なものなんじゃないかなという気がします。
古谷:変なものなんじゃないかなとは思いますけどね。
柴崎:東京の坂があるところや、八王子を歩く面白さも、複雑な組み合わせの面白さなので、すごくよくわかるんです。けど、むしろわかり易いのかもしれないなと思って。そういう平べったい、茫漠としたものの面白さのほうが、より変なものが潜んでいるんじゃないかなという感じがするんですけど。
古谷:かなり変ですね。普通に眼の中に落ち着いてくれないから、かえって見えないというか。その変さを見ちゃうとあまりにも変なので、変さを見ないように遮断しているのかなと思うんです。唐突にTSUTAYAがたっていたりする。変といえば変。しかも僕が生まれたところなので、生まれたころは田んぼがずっとあって、山までずっと田んぼだったところが全部家が建っているという。でも位置関係的には一緒なわけですよ。道とか一緒だし。そのズレをどう処理していいのかよくわからないというか。ずっといたわけではなくて25年くらいいなかったので。子供の頃に小学校を通った道を歩いていて、どこなんだろうか、とわからなくなる感じがあるんですよ。
柴崎:その感覚はよくわかるような気がする。そのズレみたいなところの間にあるのが小説なのかなという気がして。小説というか、すべての作品みたいなものはそういうところから発生するというか、そこにしか存在しないんじゃないかと思う。『春の庭』にしても、写真集の中の家と、現実にある家と、アパートの部屋の形は一緒だけど違う人が住んでいると全然違う空間になっているとか。そういうズレとズレとの隙間みたいなところが、パノラマ写真自体もそういうものだし。幽霊もそうだと思うんですよ。幽霊もうっかり現実の世界に、時間のズレみたいなところにうっかり見えるものなんじゃないかな、という気がしていて。その間に、何かしらあるような気がするようなものを辿っている。わからないからなんとかしてそれを掴みたいみたいな感じ。だから小説を書いているようなところがあるんですけど、古谷さんの作品もそういう探りながらやっているものなのかなと。
古谷:柴崎さんの小説のなんというか「向こう側感」というか。ここじゃない、「そこ」を意識している感じは常にある気がするんですよ。そこっていうのは向こう側という感じでもなくて、「そこ」っていう感じ。その仕掛け方がすごい。『春の庭』でも写真集があって、家があって、しかも主人公じゃないけれど、西さんが気にしているのは風呂場じゃないですか。何故そこをそんなに気にしているのかわからないですけど、何故か「そこ」はたんにそこで、超越的な場所では別にないみたいな。そういう感じが常にある。初期の頃の作品とかって、たぶん大阪に住んでいた時は東京に遊びに行く話をよく書いていて、東京に出てからは割と大阪が舞台の小説が多いみたいな、そういう変な感じが常にあるのは面白いと思います。
柴崎:それは東京に引っ越してからより一層意識したことで。自分が東京で何年も住むにつれ一番感じた事。そんなことを思うとは予想していなかったけれど、一番変わったことが「大阪に自分がいない」ということに気が付いたということですね。私はずっと大阪に生まれ育って、大阪に一生いると思っていたので、大阪に自分がいないということを考えたことがなかった。すごく密接に繋がっているものだったのに、東京に来て何年か経つと、どんどん変わっていくわけです。お店は入れ替わるし、大阪駅は再開発で別の場所のようだし、友達の子供は大きくなっていく。その感覚を得たことが一番大きかったというか、自分のいない大阪で時間が経っていくっていうことが一番大きかったです。だからずっと分身が、大阪にいたバージョンの自分が仮想としてある。いや、ないのですけど、そんなに考えるわけではないですけど、何か空白みたいなものがずっとあって。それが大きいのではないでしょうか。でもその感じって、たぶん「自分が死んだ後も世界が続いていく」感じにかなり近いですよね。別に大阪はすぐ行けるんですけど、やっぱり自分が住んでいた感じのその場所ではない。だから自分が死んだ後も世界は続いていくんだ、という感じを疑似体験している。その感覚を持つかどうかって結構大きいじゃないですか。その感覚が色んなものに繋がっているのではないかと思います。もともと場所に関心があって、「ここ」と「そこ」の関係性は大きなテーマです。
古谷:そういう関係性が、例えば『春の庭』だったら西さんとお姉さんの間になんかある感じがします。
柴崎:もともと『春の庭』は西さんとお姉さんの話だったんですよ。最初は西さんの話、その次は西さんとお姉さんというか、西さんと友達の話だったのを、何度も書き直して今の形になりました。
古谷:太郎とイチローって似てないですか?感じとして。小説の装置としてというか。
柴崎:そうですね。名前も似ているし。太郎もイチローも言ってみればちょっと空洞的であって、故に人が寄ってくるみたいな役割ではあると思います。
古谷:イチローの部屋とかすごいですもん。よく考えたなと思って。
柴崎:なんでしょうね、自分でも書いているうちになんとなく出てくる。
古谷:階段が2本あるって凄くないですか?
柴崎:ああいうのは書いているうちに出てくる。あとから自分が何でそんなことを思いついたかはわからないのですけど。それこそ太郎もイチローも交換可能というか、もっと抽象的な人物なのかなっていう気はしますけど。はっきりした個性や強いキャラクターではなくて。
古谷:倉庫に住んでいるのは結構(個性が)強い。強いっていうか倉庫に住んでいることによってイチローというキャラクターに納得するというか。
柴崎:最初は考えていなかったですね。間取り図は描いたんですけど、イチローの部屋はここっていうだけで。階段はすでに2か所ありましたね。内装はその時に考えて出てきた。空洞とか、何かがないということを書くのはとても難しい。それこそ八王子とか東京みたいな坂道があって複雑な風景のほうが描きやすくて、平塚とかロサンゼルスみたいな、だだっ広い、平べったくて線みたいなものを書くほうが難しい。今どちらかというとそれが気になっているのかなという気がします。ないからこそそこに何かある感じがする。
古谷:柴崎さん最近書き方がずいぶん変わっていますよね。割と前の小説って、最初に、ものすごく厚い描写があってその世界にガッと入っていく感じだったけど、これ(『パノララ』)とかって普通に語りですっと入っていく感じ。全体的にも描写の意味が軽くなってきているというか、前ほど重要ではなくなっていると思うのですが、それはどういう感じなんですか?
柴崎:自分でも色々やってみたいというのがあるのですが、できるようになってきたのではないですかね。シーンじゃなくて語りを書けるようになったっていうところなのではないかと思います。それで語りとシーンがうまく融合してくれればいいな、と思っていたりするのですけど。色々小説を読んでいて、小説の語りって変だなって思うところが一層自分の中で強くなってきて。語りをどういう風に書くか、というか、小説ってみんな結局伝聞なんじゃないかなと思って。誰かがこう言っていた、昔こんな人がいてこうだったらしい、みたいな、ほとんどの小説って伝聞のさらに伝聞くらいの感じなんじゃないかなと考えていて。なんでこんなに伝聞形式になっているのだろうっていうところに関心があるんです。『ボヴァリー夫人』(ギュスターヴ・フローベールによる1856年の小説。不倫を重ねるボヴァリー夫人の生涯が描かれている)の始まりがすごく変なんです。最初「私たち」の教室に転校生がきてっていう場面から始まるんですけど、その「私たち」ってどっか行っちゃうんですね。最後にまたちょっと出てくるんですけど。転校してきたのはボヴァリー夫人でもなくてボヴァリーさんで、その少年時代の教室にいた誰かの視点で始まっている。ボヴァリー夫人が結婚するところからの人生が語られて、最後一応こうなったらしいというのは書かれているんだけれど、途中一切「私たち」らしき人物は出てこなくて、ほとんどの部分は三人称小説なのに、「私たち」という視点を置くことによって「伝聞」としてくくられている。
古谷:小説が結局伝聞っていうのと人物が入れ替え可能っていうのは結構近いことのような気がする。近いっていうか繋がっている感じがしないですかね。
柴崎:それはもう少し頑張ってもらって『偽日記』に書いてもらって、そうしたらまた読んで考えます。まだそこまで私の中では今すぐ「あ!本当ですね!」とはならないので、もう少し聞きたいです。
古谷利裕(ふるや としひろ)
1967年生まれ。画家。2008年、デヴィット・リンチ、岡崎乾二郎、保坂和志等々を取り上げた初の評論集『世界へと滲み出す脳 感覚の論理、イメージのみる夢』(青土社)を刊行。その他著書に2009年『人はある日とつぜん小説家になる』(青土社)2014年『フィクションの音域 現代小説の考察』(BCCKS Distribution)がある。偽日記@はてな
柴崎友香(しばさき ともか)
1973年大阪生まれ。映画化された『きょうのできごと』で作家デビュー。2007年に『その街の今は』で第57回芸術選推奨科学大臣新人賞、第23回織田作之助賞大賞、第24回咲くやこの花賞受賞。2010年に『寝ても覚めても』で第32回野間文芸新人賞受賞。第151回芥川賞を『春の庭』で受賞。著書に『青空感傷ツアー』『フルタイムライフ』『また会う日まで』『星のしるし』『ドリーマーズ』『よそ見津々』『ビリジアン』『虹色と幸運』『わたしがいなかった街で』等多数。
柴崎友香よう知らんけど日記WEB 公式サイト