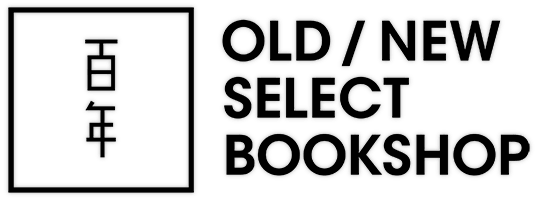百年「と」トークイベント
古谷:油絵具がいいのは色がかなり複雑に作れるということ。使い慣れているというのもあるし。絵の具を練っているの、楽しいんです。笑。チューブの絵の具だと硬さが決まっているので、顔料を混ぜたりとか、メディウムを混ぜたりして硬さを調整して。ナイフでこう、ちょっと硬くしすぎたかな、って。硬さによって色の表情も変わってくるので、楽しい。笑。
柴崎:作業っぽいことがある仕事は羨ましいと思います。小説を書いていてあんまりそういう楽しみはないので。書いていて、キーボードを押しているのが楽しいとかはないので、羨ましいです。そして、せっかく私の本が置いてあるので、何かしら伺ってみようと思います。

古谷:例えば『春の庭』とかって、決まった空間があってそこに色んなものがすごい勢いで出入りする。拾われた鍵と北海道から送られたママカリが交換されるとか。
柴崎:物々交換。人にもらったアパートの話なんですけど、アパートの住人が主人公で「太郎」っていうんです。太郎が、人にもらったものを自分で使わないでまた別の人にあげる。もらったお土産物が魚の干物で、魚は嫌いだから別の人にあげる、みたいなことが多い話なんですよ。
古谷:それだけじゃなくて人がいっぱい移動する。北海道から東京に来て、福岡に行くとか。
柴崎:同僚が静岡から東京に来て、結婚して釧路に行く、姉は大阪から名古屋に移住して東京に遊びに来る。
古谷:そうやってフレームがあってフレームの中に色んなものが入ったり、出たりしている。その感じは、なんかこれ(古谷さんの展示作品)に近いような気がするんですよ。勝手に。笑。そんなことないですかね?
柴崎:そうなんじゃないですかね。笑。難しい。ちょっと今判断できないですけど。演劇的ではあるんですよね。時々、演劇や映画の脚本を書いてみないですか?って言われるんですけど。で、それぞれ特徴があって、小説と全然違うなってまず思うのが、時間が決まっているっていうこと。時間の制限がある。映画とかテレビ、どれも。テレビドラマが一番制限ありますよね。45分で、CMが入っていたり。テレビは短い番組の構成のバイトをしていたことがあるんですけど、そこが一番違うなと思って。演劇は一番何が違うかっていうと、一つのところを出たり入ったりするわけですよね。舞台自体は動かなくて。一番違うところで、難しいと思ったんです。小説はその点緩いメディアで。時間の長さも自由だし。映画だって延々何時間もとってもいいですけれど、それでもやっぱり時間がある。時間がフレームっていうことなんですかね、映画は。一つの空間に出たり入ったりするのが演劇なんだなと思う。それに少し近いのかもしれないですけど。物々交換は『わらしべ長者』みたいなことがやりたかったんですよね。でもあんまり長者になれないけど。書いている間に、何かもう少しいいものを貰えたりするかな、と思ったんですけどね。
古谷:でも結構いいもの貰ってないですか?
柴崎:最後ソファー。
古谷:ソファーとか冷蔵庫とか。
柴崎:長者っていうほどのものではない。貰えたら嬉しいですけど。笑。
古谷:最初全部貰いものじゃないですか。ママカリ(魚)から始まって。
柴崎:そうですね。
古谷:最初全部貰いもので最後あれだけ貰えるのはすごいです。
柴崎:なんか昔ばなしみたいなものを書きたいなと思って。そういう話が好きなんですよ。『三年寝太郎』とか。寝ている間に良いことがあるみたいな。でもそんなに良いことが起こってくれなかったんですよね、現代の東京だと。
古谷:例えば登場人物の関係で、主人公の太郎と同じアパートに西さんという人がいて、太郎のお姉さんと同い年で、もう一人の住人の巳さんという人はお父さんと同い年なわけですよ。それで西さんがいなくなるとお姉さんが出てくる。形式として一人二役というか、フレームのなかで同じ形が別の色で入れ替わるみたいになっている。そういうのが結構多くないですか?
柴崎:それは意図して書いています。お姉さんと西さんは同い年でお父さんと巳さんとニール・ヤングが同い年なんですけど。あと隣の森尾さんと職場の同僚は北海道に関係があるとか。共通のところがいろいろあるように。
古谷:そうすると、それぞれの人物がその人なのだけれど他の人でもある感が色んなところにある気がするんです。
柴崎:そうです。
古谷:そういうことって結構重要ですよね。そういうことを僕も作品で考えているつもりなんです。
柴崎:この型紙のキャラクターっていうのは、かなり交換可能なわけですよね。反転してもいいし。でも結構人間も交換可能なんじゃないかっていうことを考えているところがあって。それが気になるというか。
古谷:作品は一枚一枚みんな違うんですけど、同じパーツでも組み合わせが違うことによって固有性が出ている、みたいなことが、柴崎さんの小説の人間同士の関係の作り方とかに近いものを感じることがあって。『パノララ』でもいっぱい登場人物が出てくるんですけど、母親と娘の関係が複数あって反転的にクロスしている。例えば、主人公の田中真紀子さんにとって、みすずさんがカリスマであるとしたら、みすずさんの娘である絵波さんにとっては、吉永がカリスマみたいな。あと、みすずさんのもう一人の娘の文さんと真紀子さんは割と近い境遇にいるけど、母親の性格は全然違うというところでクロスしているとか、同じような関係性が反復したり反転したり一部だけ違っていたり、そういう形式的な操作がいっぱいあってできているような。その中で、例えば『春の庭』の最後に唐突に「私」という一人称が出てくるとか、『パノララ』の最後で同じ日が反復するという状態が準備されるというか、そういう操作によって生まれてくる感じがしました。あと結局これって両方ともかなり家族の話だなって思って。『春の庭』は、最後お父さんを埋葬するような話になっているじゃないですか。
柴崎:はい。
古谷:それを準備する過程としてフレームの中にいろいろ出たり入ったりするっていうのは、入れ物があって、魂が出入りするみたいな感じがあるように思うんですね。それはどう?
柴崎:はい。さっき少し人間も交換可能なんじゃないか、みたいな話をしましたけど、本来は、かけがえのないものとしてとらえるのが人間的な考えという感覚があるかと思うんですけど、ずっと気になっているのが新藤兼人の映画で、初期の作品はずっと殿山泰司が出ているじゃないですか。それで殿山泰司が死んで、しばらくするとそこの位置が六平直政になるんですよね。そうか、これでよかったんや、って思うんですよね。殿山泰司はいなくなったけど六平さんでええねんな、と。きっと新藤兼人が「あ、なんか代わりがいた」と思ったんじゃないか、と、その感覚にとても興味がある。乙羽信子の位置は大竹しのぶが演じていて、ここはかなり印象が違うのですが、音羽信子が大竹しのぶを指名したらしいです。新藤兼人の映画の中にいる六平直政は殿山泰司であり、六平直政である、という感じそのものよりは、新藤兼人がそう捉えていたんじゃないかということが気になるんです。基本的に俳優ってそうですよね。自分ではない人の代わりをやるわけで。同じ役を何度も別の人が演じたり。そこに何か興味がある。家族っていうのも一つの形式、フレームみたいなもの。家族っていう形の演奏というか、ちょっとずつ違うバージョンみたいな描き方を試みたのが『パノララ』かもしれません。木村家の母親・みすずさんは女優ですし。