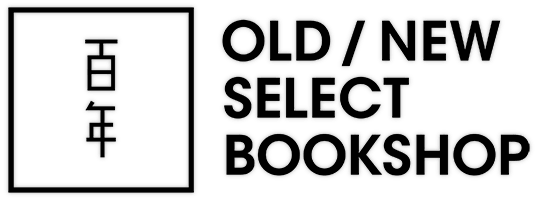百年「と」写真~写真と芸術の界面から~ 2
町口・でもなんで、日本の写真界は野島に何もしなかったんだろう?
光田・写真はやっぱりすごくイデオロギーだらけなんですよ。ノー・トリミングでスナップショット、これが写真の王道ですよね。
町口・(その期間が)長すぎるよね(笑)。
光田・写真っていうのはひとつのメディアですから、それを使って何をやったっていいと思うんですよね、やりたいことがあれば。なのに、「王道」イデオロギーがものすごく強い。写真教育の現場には、やっぱり今でもそのイデオロギーの影響は消えてないんじゃないかなと思います。やっぱりノー・トリミングのスナップが上手な人は写真が上手な人なんじゃないですか。そういう反射的な名人芸みたいなところに、写真の本質をいつまでも置いておく必要はないと思います。何をやったっていいはずなのに。野島の頃の写真家はなんだってやってるんですよ、できることを。例えば、野島の場合はインクを使った印画とか、手作業で色々なところ削ったり強調したりとか、そういうことを普通にやってましたし、ひとつのネガからほんの一部を取り出して大きなポートレイトを作ったりとか仲治がよくやってましたよね。とにかく何でもやってるんですよ、フィルム切ったりとか、乾板を自分で作ったりとか。でも写真の王道は外さないっていうイデオロギーはすごく強くて。例えば言葉を使えないとか。マッチアンドカンパニーの写真集は言葉がすごく少ないですよね。
町口・ほとんどいれないですね。
光田・なぜ?
町口・やっぱり言葉と写真は違うからね。以上。
光田・言葉と写真が違うということは、写真はこうだっていうお考えがはっきりあるわけですか?
町口・はっきりあるというか、やっぱり言葉と違うっていうか。自分がMっていうレーベルから出している写真家は僕と世代がすごく近い写真家たちなんですよ。みんなやっぱり言うんだよね、言葉にできないことっていうのが写真なんだってみんな信じてて。俺もそれ信じてて。言葉になるんだったら写真撮ってたってしょうがないじゃんっていうのがあって、だったら印刷物として発表していくものも言葉っていうのを抜いた状態で見てもらう。まあこれは後で話そうと思ったことでもあるんだけど、写真集を見る教育がないと。写真集が売れないとかいう話があるじゃない、俺も写真集好きだけど冷静に考えると写真集を見るっていう教育がないなあと。写真とかだったら露出とかさ、写真学校だってあるじゃない。だったら写真集学校とかあってもいいかなと思って。めちゃ面白いわけですよ、写真集って、見方によっちゃ。見るっていうか読んでるんだけど、写真集は。
光田・やっぱり読んでいるわけですよね。
町口・言葉じゃないけどね。
光田・やっぱり読み方っていうのがあると思うんですよ。
町口・そう、でもやっぱ読み方をみんな知らないんだよ、意外に作ってる方も知らないから。そこらへんがぐちゃぐちゃになってきちゃってる。どれから見ればいいのかわからないとかいう話になっちゃう。写真集の本ってあんまりないんだよね、順を追って説明してくれるような。そういうのに最近興味あるんですよね。一昨年くらいからパリフォトにブース出してるんですよ、パリフォトいいなあって思うのはバギーカーに子供乗っけてくるんだよね。うちのブースの前に止まって、子供に写真集見せるんだよ。日本にはそういうのないよね。写真集に言葉をいれるいれない以前の問題があって、そこをやりたいなあと。
光田・なるほど。絵でも割とそういうこと言う人いるんですけど、黙って見ればぴたりとわかるみたいな。
町口・わかるわけないじゃん。
光田・違うと思うんですよね、私なんか十数年やったってわからない。文字の場合とどう違うのかうまく説明できませんが、ヴィジュアルなものでもやっぱり読むということはあると思うんです。一枚の写真を長く見る、長く見たいような写真をですよ、一枚の写真を長く見るということはどういうことか、何を見るのか、そこから何を読み取るのか。黙って見れば何かを感じられるだろうとかそういうものじゃないですよね、それだとやっぱり長くは見れないんですよ。だけど、全部の写真じゃなくて本当に見たい写真をもう一度見て、それが何かを考えたいわけですよ。写真集もそうだと思う、何回でも見れるんだから。
町口・どっからだっていいしね。
光田・どっからでもいいんですけど、やっぱり順番が考えられてるんですよね。
町口・考えられてる。めちゃくちゃ密ですよ。
光田・考えられてるってことも頭にいれながら、こう考えてこれとこれは見開きかとかいうことを読みながら見ていくのが、写真集の読み方のひとつでしょうね。展覧会もそうですよね、ただそこに置いてあるだけじゃなくて、一応最初にこれを見てもらってこの部屋に立ったときはこれが見えるようにとか、これとこれを関連付けて見てもらえるようにとか考えて置いてある。一点の一点のものを長く見るときの読み方と、それが並べられたり編集されたりしたときの読み方っていうのは、同時にいくべきだと思うんですよね。天から降ってきたものなんてないわけですから。誰かが七転八倒して作ったものが、色々な理由があってようやく見てもらえるようになったわけですから。その色々なことを含めて読めるようになってくると楽しいですよ。
町口・いいじゃんこれ~ってやってるんじゃないんだよね。寝れないんだよ。いいじゃん、この感じとこの感じとかじゃないんだよ。もうずーっと考えるんですよ。
光田・その考えってなんですか?
町口・それはさっき光田さんが良いこと言ってたんだけど、一枚の写真を見るっていうことだよね。一枚の写真にはさ、もちろんそれは良い写真なんだけど、写ってるんだよ。
光田・そうなんですよ、写ってるものが何なのかは口では言えないんですけどね。
町口・でもそれをね、書き出すようにはしている。
光田・ほら、やっぱり言葉でやってるんじゃない。
町口・言葉でやってるか(笑)、メモるよ、一枚の写真に対して。すぐ捨てますけど。そういう意味で言うと、俺が写真集作ったのって佐内正史の「生きている」っていうの、あれが俺初めて作った写真集ですよ。
光田・(写真集を作るときに)確信とかってありますか?これでいいんだ、みたいな。
町口・それが印刷、やっぱ確信にしちゃうっていうのが印刷。その気持ちが俺わかるから写真集好きなんですよ。必ず確信してるから。あ、でもあれがあるか、この前のロバート・フランクの「アメリカンズ」の展覧会。「アメリカンズ」っていうのが結構研究されてて。「アメリカンズ」ってやっぱ写真集じゃないですか、ほぼインプットされているのが写真集。でも、「アメリカンズ」って出版社が変わって幾度となく再版されてるんですけど、ロバート・フランクってそのときトリミングとか、版型とか、写真を変えてることすらある。そういうことがこの前の展覧会で随分資料とか出てて、あれはやっぱり勉強になりましたね。「アメリカンズ」なんかは写真集を勉強するのに良いかもしれないですね、わかりやすい。
光田・あとで森山大道さんの話も出てくるとは思うんですけど、森山大道さんっていうのは、わたしもすごく大好きな安井仲治さんにすごくシンパシーを持っているってことは勇名なんですけど、なんでそんなにシンパシーを持ってるかというと、安井仲治のコンタクトを見たんですよ。コンタクト見るっていうことと、写真を見るっていうことが写真の表と舞台裏みたいなところがあって、森山さんも勿論安井仲治の写真展もご覧になるんでしょうけど、普通は発表しないコンタクトをざーっと見たということが、安井仲治がすごく特別な写真家として森山さんのなかに入っていく一つのポイントになっているんじゃないかなと。コンタクトっていうのはすごく生なものですよね、撮ったフィルムをそのまま焼き付けたものなので、そこからトリミングもしていないし、選びもしていないし、ただ視線や身体の動きがそのまま出ているような。その生な材料に森山さんはすごく反応してるんじゃないかと。
町口・安井仲治のベタとか見たことないなあ。
光田・ベタがあるんですよ、それが70年代に安井研究に着手された福島さんという方が色々な方の協力を得て作られたコンタクトで、数少ないんですけどやっぱり非常に素晴らしいです。コンタクトを見ることによって写真家を評価するというのもひとつあると思います。だけど、私はコンタクトの中から何を選んで、どんな風にしたかということ、それが彼の作品だと思うので、私はどちらかというとそのフィニッシュの方に重きを置きたいんですよね。
町口・愛があるなあ。
光田・(笑)安井仲治といえば、モダン・プリントのポートフォリオを作っているところなんです。オリジナル・ネガから新しくプリントを作るんですけど、印刷物じゃない写真のマテリアルの魅力みたいなのもやっぱりあるんですよね。
町口・もちろんありますよね。モノとしてみる。そうすると、理由ができるんだよね。暗部のデティールの出方から今度製版の角度変えてみようかなあとか、そういうところに凝れるんだよね。そういうときに写真がというよりも、物質としてはすごく気になります。
光田・例えば、1930年代には写真は油絵と違ってマテリアルがないって言った板垣鷹穂という評論家がいましたよね。彼は、写真にはマテリアルがないんだから印刷しても写真そのものでも同じだと。よって、写真は印刷物になった方が社会性もあるし、大衆性もあるし、芸術的なプリントにこだわるのは良くない、写真の本道から外れているというひとつのイデオロギーが発生するわけですよね。でも、この間安井仲治のポートフォリオを作るにあたってフェロがけをやったんですよ。安井仲治の時代はフェロがけを非常に好んだ時代でもあって、70年代までくらいはされてたんだけど、今はフェロタイプの乾燥機も製造中止になっていてラボでも使えないんですよ。でも、安井仲治の代表作のシリーズ「流氓ユダヤ」シリーズを見て、これはフェロがけだろって思って、フェロがけだと表面に光沢がのって、黒目が涙目の状態になる。黒が漆黒のとろりとした感じになる。表面を光沢するとか、そのちょっとのやり方で見方が違ってくるじゃないですか。だから、やっぱりみんな出来るだけのことをやってきたんですよ、もっとここを濃くとか。印刷も結局は手仕事みたいなもんですからね。
町口・手仕事どころの騒ぎじゃないですよ。大変ですよ。最近活字がなんだとか、活版だとかあるけど、そんなのは当たり前で。オフセットにしたってやっぱり手ですよ。
光田・そうですよね。昔は、写真は機械的な作業なので、絵と違って誰がやっても同じだっていう考えもあったんですよ。でも、誰がやっても同じなわけがない。印刷もそうで、印刷だって機械がやるんだから、誰がやっても同じだって思うじゃないですか。でも、オペレーションの人がどんな人か、どれくらい懸命かによって違ってくる。結局は機械を使って人間がやってることですから。写真も印刷機も道具で、それを使って何をやるか。
町口・光田さん、話合いますね。俺もデザインの仕事をしていて、マックとかあるわけですよ。俺は18歳からこの仕事をやってるんで、マックはなかった。そのとき、1ミリの中に10本線引けって言われてさ、引くわけですよ。手とか体を使う。マックだって三角定規と一緒なんだよ、だけどみんなデザインがマックの中に入っていっちゃう。三角定規の方が強いっていうか、三角定規にデザインさせられちゃってるっていうか、三角定規って道具じゃんみたいなことを忘れてる人が多い。光田さんが言うように印刷機も道具でさ、人がやってるものだから。紙とかもそうだし。
光田・そうなんですよね、全部人が動かしているもの。なのに、写真は機械や科学の反応だから手仕事じゃなくて芸術じゃないっていうイデオロギーが、野島や安井の時代は結構あった。かといって、そこに手を入れると写真の王道から反してるとかもあって。どんどん領域を狭くしていって木村伊兵衛的な王道以外はダメみたいな感じが結構長く続いてますよね。でも、もっと自由だし何やってもいいし意味わからなくてもいい、誰にも注目されなくてもいいし、誰も知らないところの扉を開けてもいい、そういうものとして私に写真を教えてくれたのが野島さんや安井さんだったんです。
町口・そうですよね、そこらへんはしっかり本に書いてありますよね。ちょっと照らし合わせたのは、ノイエ・フォトとかのドイツの写真家たち。想像では上から見たらどうなのかなっていう時代に気球とか飛行船とかできて上から撮れるようになったりして機械文明の影響を受けてる。時代は一緒だから結構福原さんだってパリとか行って影響受けてますしね。俺は最初にドイツの写真に魅力を感じて、で日本では同時代で野島とかがいて、うわ~同じ時代かあっていう。
光田・すごい同時代性ありますよね。写真が共通メディアだからっていうこともあるんだと思うんですけど、当時から海外の潮流だからといって関係ないものとは思えない。まさに自分の世界で起こっていると同時代的に感じられる、写真はそういうメディアでもある。同時代性がピタッとくると時代は変わるし、野島はその頃40代でやっぱり自分を変えようとする。自分を変えようとするところがまたいいですよね。自分が今まで思ってたものと違うものが出てきて、時代も違ってきて、印刷も違ってきて、道具も違ってきて、ライカになってきて、その時に自分をどうするかですよね。今までの俺を守るとかそういう人もいっぱいいる、最先端の職業カメラマンとか広告カメラマンとかは新しい方にいくだろうし。その時に自分はどうするか、そこで色々な人のポジションは問われたと思います。
町口・それっていつの時代も、今もそうですよね。1920年代とか戦前だからとか戦後だからとかではなくて。
光田・いつもそう。いつも違う選択肢がやってきて、自分が思ってたものと違うものとであって、そのときにどうするか。そのときに昔の人がどうしてたかっていうのが気になる。
町口・気になるよね、すごい参考にするよね。一回入れるよね。それは俺もやってる、入れないと出ないから。出たら俺だみたいな感じで、いけしゃあしゃあとやってる。この時代も今の時代も、そういう意味では変わらないものもあるんですよね。
この第一章(光田由里著「写真、『芸術』との界面に」)って中平じゃないですか。
光田・中平はすごく戦前写真家的なものを持った戦後の写真家だったと私は思っています。だから、彼をこの本の最初に書いたんです。
町口・この前「来るべき言葉のために」が復刊されましたね、あれは良かったですね、見れる機会ができたから。先人のやつを入れようとたって見れないと入れようがないじゃない。
光田・あの七転八倒がいいんですよね。彼も写真のイデオロギーと自分と闘っているんですよね。
町口・戦前から戦後の架け橋みたいな存在だとやっぱり大辻さんになるんですかね?
光田・そうですね、私にとって大辻清司さんはすごく重要な作家ですね。写真家としての姿勢がすごく素晴らしいと思う。大辻さんは、迷う写真家なんです。彼は少年時代が戦時中で、紙飛行機作ったりとか天体写真を撮ったりっていう科学少年。古い雑誌で瀧口修造が紹介していたシュルレアリスム写真について勉強することから自分を創っていった人なんです。敗戦後何もなくなった世の中で、シュルレアリスム的写真から自分を始めていく。そうしているうちにすぐに中平卓馬とかが登場しちゃうんですよ。「え?」とか思ってると、次はコンセプチュアルな写真とかも出てくる、そのときも「え?」とか思う。彼は、美術の展覧会の会場撮影もしていて、現代美術作家の「え?」みたいな作品も写すわけですよ。東京ビエンナーレなんかでも、「これが作品?」ていうような鉄のくずを床にまいたようなものも撮影する。そのときに、自分が今まで作品だと思っていたものとは全然違うものとであって、自分が今まで写真だと思っていたものとは全然違うものとも出会っている。そのときにすごく迷っていて、文章を書きながら自分を確かめることで一歩一歩前に進もうとした人なんです。例えば彼の友人の石元泰博さんは、圧倒的な造形力があるので迷う必要がないようにみえる。何があろうと。でも大辻さんは迷う、そこが大辻さんの現代性だと思うし、戦前と戦後の新しい写真を繋ぐ役割を果たした理由だと思う。
町口・大辻さんは若いお弟子さんとかも多かったんでしょう?
光田・そうなんですよね。弟子の最年長が七十何才とか(笑)。あとは、有名なお方だと畠山直哉さんとか牛腸茂男さんとかもそうですよね。
町口・そこらへんから俺は入るんですよ。俺の父親がグラフィック・デザイナーなんですよ。父親はすごく写真集が好きだった。俺は学校が嫌いで、学校来るなって先生から言われてた。だから、父親の仕事場が遊び場だった、それが俺と写真集との出会い。父親は今73歳なんだけど、大辻清司さんの家にも行ってたらしくて、何かの仕事で一緒になってそのときに大辻さんから見せたい写真があると言われた。それが田村彰英さんの家のシリーズのプリントだった。それが出会い。それから田村彰英さんとか牛腸茂男さんとかと繋がりができて、デザイナーと写真家という関係ができていったらしいんですよ。
光田・町口さんの原点ですね。
町口・そうですね。田村さんのデビュー写真集なんかも父親がデザインしてるんですよ。このシリーズは松岡正剛さんの「遊」の創刊号にも載ってましたね。デザインは杉浦康平さんで。美術手帖には「午後」ってシリーズが載ってた。このシリーズは、「M/lightレーベル」っていうのを作って、うちの弟もデザイナーなんですけど、名前が風景の景でヒカリっていうの、その弟がやってるのが「M/lightレーベル」。俺たちに影響を与えてくれた先人たち、60年代くらいまでいっちゃうとちょっと違うんですよ、やっぱりそういう人は自分の父親世代だから70年代くらいの人が身近で。死んじゃった人はやらないっていうのはとりあえず決めてて。なんでかっていうと会えないから、会えないと話ができないじゃない。話をしないとやる意味ない。当時の話とかをみっちり俺らがして、写真集にアウトプットしていかないと意味ないなって。生きていて、現役で運動し続けていて、俺らがその人たちに会いに行って、話をして、しっかりアウトプットするっていうのが「M/lightレーベル」の趣旨。
光田・町口さんと同世代の写真家たちから始めた写真集製作が、今度はルーツにより迫るようなことをされてるんですね。
町口・それってすごく面倒臭いんですよ、でもやっぱり面倒臭いことやらないとものづくりにはならないなとも思う。だから、そういうものをしっかり作っていく。あとは始めたんだから続けようぜっていう礼儀もある。そういうものがあれば、若いやつに勇気が与えられるのかなみたいな。結局若いやつらのためにやってるんですけど。そういうことやってると、ちょっとは明るいかなと。