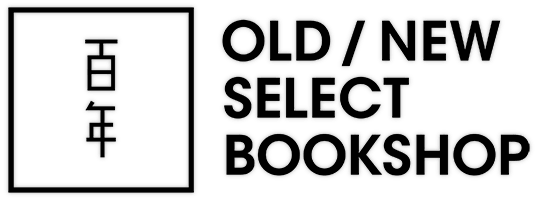百年「と」写真~写真と芸術の界面から~ 3
光田・私は死んじゃった作家の研究を結構やっていて、研究するためには色々な人に会ったりとかが原動力になったりもするんですけど、そういうことをやることによって今に役立てたいっていうことが当然あるわけですよ。だから、今の写真にも興味を持ち続けたいし、参照点として歴史的な人たちの仕事を生かしたいという気持ちがあるので、町口さんがされていることにすごく共感できます。例えば、大辻さんの家で田村さんとか牛腸さんが出入りしていた頃って、意外と美術と写真の間の距離が狭かった時代だと思うんですよ。今は写真誌と美術誌って分かれていて、読者も違うような気がするんですけど、70年代の初めのある時期だけ違った。中平さんなんかはリー・ウファンや赤瀬川原平など美術の関係の方々とすごく近かったし、大辻さんは美術の仕事をしてたから美術と写真の両方を見ながら自分の立ち位置を模索した人だったから、新しいものが出てきたときに見せる人がたくさんいた。美術手帖が1968年の12月号で初めて写真の特集(「写真、今ここに」)を組んだ。まさにプロヴォーグの時代。その後の数年間だけ美術と写真がすごくリンクしてた。
町口・俺が思うのは、60年代って編集が入ってきたなあっていう印象なんですよ。中平さんとか特に編集者っていうものの存在を感じる。中平さんなんかはもともと写真家じゃないじゃない。「現代の眼」に編集者としていてさ、色々なやつに会うわけじゃない。そういうのを見てると写真集っていうのが動き始めてる気がする。編集的な要素のある人間が入ってくることによって、ものすごく日本の写真集が良くも悪くも活性化していったっていう感じ。面白いものがそこからグワーって出てくるみたいな。
光田・そうですね。昔からあるアサヒカメラとかそういう感じとは違って、カメラ毎日なんかにも名物編集者の山岸さんっていう人がいたりして。
町口・編集者っていうのが絶対切って離せないんだよね、そこらへんの時代から。そこらへんからなんかザワザワするっていうか。
光田・そうですね、雑誌でいっても確かにそう。例えば、「季刊 写真映像」とかもありましたしね。写真集の装丁も黄金期といってもいいくらい。例えば、「鎌鼬」も田中一光さんとか横尾忠則さんとかの装丁ですよね。ああいうスターっぽい人が写真集をどんどん手がけていく。
町口・そこに杉浦康平さんとかもいるしね。そこらへんの仕事は俺も興味がありますよね。それまでは写真集って写真の記録集というか、変な話カタログみたいな感じというか。まあ、写真があって複製して本にしましたみたいな感じだったんだけど。もはや物質としての写真集みたいな見方がより強くなりましたね。あのままカタログ的な見方しかできなかったらちょっとやってなかったとは思うけど。写真集は見るよりも作るほうが面白いんだと思えた。そう考えてみるとここらへんの写真集ってやっぱり色々やってて面白かったですよね。
光田・写真集の表現力みたいなものがどんどん強くなっていったと同時に、写真一枚の描写力っていうのをかなり抑える時期でもあったんじゃないでしょうか。例えばプロヴォーグなんかは非常に強い表現力で、アレ・ブレ・ボケで何が写ってるかわからないような感じだったし。
町口・あとやっぱあの時代は俺は杉浦康平さんの仕事かな。高梨豊さんの「都市へ」とかね。「都市へ」ってもはや写真より写真集が素晴らしい。なんでこれ全部対向ページをグレーにしたのかなとか、表紙に鉄の丸がついてるのとか。そういうことにどんどん入っていけた。相当影響されてますね、あそこらへんには。
光田・なるほど。それじゃあ、さきほどの「M/lightレーベル」なんかはまさに町口ファミリーの原点というか、バトンのありかをはっきりさせながらやってることなんですね。
町口・そうですね、じゃないとやってらんない。だからといって若いやつらとやらないとかじゃないんだけど。同世代との仕事と先人へのリスペクトを形にするっていうのはどっちも大変だけど、そうすれば見えてくる。
光田・例えば、70年代前後の写真って私もすごく興味があるんですが、興味のひとつはコンセプト重視みたいな時代だったっていうのがあって。写真は言葉とは違うっていうのも確かにそうなんだけど、いけるところまで言葉で思考して撮る写真もある。そういうものがこの時代には出てきている気がする。この間町口さんとご一緒した「1_wall」展で審査をしたときに、作者にどういう意図でこれをやってるかって聞くと、なんか感じてもらえたらいいなとか、この作品は完結してますかって聞くと、完結ってことはないんです、続ける限り続けます、みたいな答えが多かったんですね。私はそこに疑問を感じる。私はちょっと古いタイプなんで、作品だったら考えるとこまで考えて、人に見せるんだからここまでいったぞっていうところで見せてくださいねという気持ちもある。70年代前後で、言葉で考えられるところまで詰めに詰める、でも結局言葉では説明できるものではないんだけど、それでも詰めに詰めてぱっと見わかりにくい写真みたいなものもある。やっぱりそれは魅力的だし、そのとき言葉と写真の関係はすごく緊張感があったと思う。この間の審査のときの感じだと、言葉はいらないみたいなのを感じて、それはいいんだけど考えなくていいのかなと疑問を感じた。写真の奥と先にいく、つまり読むためには考えられた写真じゃないと読んでいけない。編集もいけるところまで考えられてるから読める。
町口・デザインもそうですよ。今日もね、俺同じ年のひとってあんまり周りにいないんだけど、最近藤本壮介っていう建築家と仕事しててね。今度INAX出版から出る本の表紙をやってて、俺こう思うよって出すと、藤本が「いや、俺はこう思うよ」って出してくる。今日も朝イチから始まって、周りから見たら気が狂ってるんじゃないかと思われるような、本当に何ミリとかなんですよ。そこを詰める。出来たときには抱き合っちゃってるんですよ。詰めて詰めてやんないとダメなんだよね、特に印刷物って。ネットだったら別にいいかなって思うんだけど、直せばいいかなみたいな。でも写真集って絶対直しきかない。やっちまうまではギリギリまで詰める。さっきの写真家との共有みたいな部分でも、俺はそれをみんなとやる。大森克己さんにしても、髙橋恭司さんにしても、やっぱりみんなとそれができる、ギリギリまでいける。お互い本気なんじゃないのかな。別に完成度を高くしようとかじゃなくて、自分の意識としてギリギリまでいって、ああでもこうでもないを繰り返して、わからなくなったら人に聞いたり先人を見たりとか、そういうことをちゃんとやって、ぼろぼろになっても、それでも次詰めてばんと出すと自ずと出てくるんですよね。まあ、さっきの話の審査での若い子たちをそういう風にさせちゃってるのかなっていう気もありますけどね。だから、さっき言ってた写真集を読むワークショップみたいなね。
光田・やっぱりそれだけギリギリまでやった藤本さんの表紙とかは見たいですよね。これがやったなんだ、っていうのを実感してみたい。
町口・そういうことが印刷物にはできると思う。他のものだとわからない。だから自分のやってる仕事なんかも良い仕事だなーって、やめられねえなって思う。
光田・写真が印刷やデザインと強力に結びついたのは、やっぱり野島とか安井仲治とかの1930年代だったと思いますね。そのときに今まで図案を描く仕事してた人が、レイアウトっていうか写真をどう活かすかってところですごい力を発揮したんですよね。それが今もある。
町口・そうそう、俺デザイナーで木村恒久さんがすげえ好きでさ。
光田・私もですよ!!
町口・中平卓馬さんの「来たるべき言葉のために」のカバーデザインでさ。で、インタビューでさ、(カバーデザインは木村恒久さんのデザインだけど)中身はどうしたんですか?っていう質問に「あれは中平だよ」って。「写真家は二度シャッターを切るから」って言ったんだよ。かっこよくない?1回は撮って、それをセレクトして並べるっていうのは、どうやら木村さん曰く写真家は二度シャッターを切るっていうことで。
光田・木村さんですごく尊敬してるのは、万博のときに太陽の塔の屋根のところに原爆写真の展示をやった。原爆の写真の展示を万博でやるっていうこと自体、万博協会が大喜びすることではなかった。日本の進歩と調和を見せなきゃいけないときに、原爆の写真を並べる。予算がないところを、色々な人を訪ね歩いて原爆の写真を木村さんが集めた。それを編集して展示した。見に来る人はそんなの気持ち悪いっていうところの尊厳を守りぬいたデザイナーですよね。あれはすごい。
木村さんって有名なデザイナーですけど、広告はやらない。物を売るための仕事は嫌なんだって(笑)。カレンダーになるような山岳写真があって、こんなみんなが使い古しているような美学を評価する山岳写真は駄目だと。これは権力者側におもねるような態度の写真だ、これをひっくり返すデザイナーこそ必要なデザイナーなんだというようなことを言うわけですよ。みんなが良いというような美学を評価するような、そんな仕事は駄目なんだということが彼のデザイナーとしてのポジションだったんですよね。歴史に残る人材です。
町口・デザイナーとしては危険ですよね。命取りですよ。俺が心に残るのは、石内都さんとの仕事かな。石内さんも最初に出した写真集は木村恒久さんがデザインして、石内さんも木村恒久さんから色々なことを教わった人の一人なんだけど、文字詰めひとつとってもよく木村さんの名前を口にする。「木村さんはもうちょっと詰めたかも」とか、それで俺も「いや、こっちの方がいいんじゃないですかね。木村さんならたぶんそうしないと思いますよ」とか。なんか面白くなっちゃって。石内さんとかも精神的な部分を木村さんからすごく影響を受けてる部分もあると思う。だから、デザイナーっていう存在も写真家との間に色々なことが起こってくるような時代が60年代後期からあって、数々の先人がいるわけじゃないですか、その人たちの話を直接聞くこともあるし、文献で目にすることもあるし、人から聞くこともあるんだけど、やっぱりそういうものを入れていくと自ずと80年代にも入ってきて、俺が仕事始めたのが80年代でやっぱりそういうものをひっぱっていって今の時代にくるような。ちょっと急ぎすぎ?まあでも繋がってんだよね、結局ね。
光田・私こんなに町口さんと話が合うとは思わなかった(笑)。それこそ誰かに言ってほしかったようなことです。
町口・いや、合うでしょう(笑)。だって木村恒久さんの話して、万博のこと話すような人ってあんまりいないよ。あんまり知られてないもん。でも、これ昔話じゃないから面白いよね。だってさ、あんときはこうだったよねっていう話じゃなくてさ、勝手にこっちで調べて言ってるだけだからね。
光田・たしかに。だから、万博の写真を撮って北代省三が写真やめたっていうのもなるほどと思う部分もあるんですよ。大辻さんも万博の写真を撮る頃には迷いが最高潮に達していて、彼は仕事でやってるわけで、仕事でやるようなピントがあっている写真とピントが合わないアレブレ写真、かたや理詰めで撮る写真とストリートスナップ、あるいはコンポラ写真。そのときに自分の立ち位置はどうしようかなっていう、そのとき大辻さんは50歳とか。迷いに迷うわけですよ。そのときに、「自分が立っている場所」のコンセプチュアルをつかむ。私はコンセプチュアルなんていうのは今そんなに流行っていないように思うんですけれども、例えば高松二郎の写真集、高松次郎は美術作家なんですけど写真を自分のアトリエとかに放っておいて、それを反射させて、失敗した複写を作るんですよ。失敗した複写っていうのは写真を無化することですよね、写真を無化するっていうこと自体がコンセプトだと思うんですけど、でもよく見ると反射してよくわからなくなっている写真っていうのが自分の奥さんの写真とか、近所の井の頭公園の写真とか。写真が置いてある場所も自分のアトリエとか奥さんの膝の上とかなんですよ。だから、すごくプライベート。つまり、コンセプチュアルなんだけどそれだけではやっぱり作品はできないんですよ。大辻さんもコンセプチュアルな仕事やろうとするんですけど、自分の机の上とか自分の家の側の代々木2丁目とか、そこでやる。定点観測とかいっても知らないとこじゃなくて、自分の家の横とか。それで、足場が作れる。コンセプチュアルなことを写真でやるとき、写真は現実しか写さないから、現実との関わりを抜きにコンセプチュアルも何もないわけですね。そのときに、コンプチュアルなものとここにある具体的な現実みたいなものとカメラを持っている自分の手が、ぐっとひとつになっていく。そういうのが高松さんとか大辻さんの写真にあると思う。それがぐーっと洗練されてくると田村さんとか。これ(田村彰英のファースト写真集)もやっぱりすごくデリケートな個人的な作品だと思う。
町口・これさ、ご存知だと思うけど、田村さんの自宅から撮ったんだってね。
光田・そう。世界で始めての写真っていうのも自分の家の窓から撮ったものですしね。だから、写真は機械が歩いていってるんじゃなくて、足と手がある人間が写しにいっているから、その人がいる場所が重要なんですね。
町口・そうですね。それも昔考えたなあ。やっぱロバート・フランクなんかもさ、ロバート・フランクがそこに立っているってわかるのがすごいよね。もはやそれだけですごい。そういう見方で写真を見るとまたすごい楽しい。ただ写っているものだけを考えるんじゃなくて、ロバート・フランクがそこに立っているっていうことを考えて、立ち位置のことを考えながら写真を見ると結構いい見方ができる。例えば、今日は車だけ見ようかなあとか、車だけ見るとうまいこと構成してるなあとかあるし。
光田・でも、そこにただ立ってるだけで何か感じて下さいとかじゃなくて、いけるところまで考えられてるから読みができるんですよね。
-最後に今後の活動についてなど
町口・僕の場合は90年代から始まってるんでしょうね。最初に作った写真集が97年なんで。90年代からゼロ年代になって、いま10年代になってるわけじゃないですか、そんときに2000年代になったときには90年代に俺が出会った人に、ああこれから生きていけるかもしれないな、ひとりじゃないんだ!って思った。結構いたんですよ、それこそ佐内とか大森さんとか野口もそうだし、みんなやっぱそのときふっと見たらいてくれたんだよね。とにかく2000年代っていうのは、そういうやつらとやっていくしかないっていうか、今後もそれをずっと続けるかなってないう。
光田・私は写真ならなんでも好きっていうわけにいかなくて。やっぱり興味あるものとそうでないものがすごくある。美術好きみたいなところもあるんですよね、多分。私が勝手に師と思っている大辻さんなんかは、なんでもない写真っていうのが良いというのが彼の思考の果てだった。私はやはり、何でもある写真の方が好きなんですよ。現代の写真で言うと、野口里佳さんの「鳥を見る」にテキストを書いたときにも思ったのが、写真っていうのはまだ見ていないものを見せてくれるんだなっていうことだった。ありえない光景とかフェイクとかじゃなくて、見たことない光景を見せてくれる。そういう写真に興味がある。だから、何でもない写真じゃなくて何かあると気づかせてくれるような写真を大事にしたいですね。