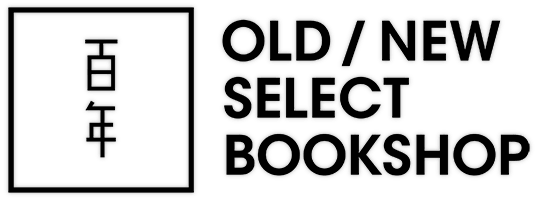百年「と」写真~写真と芸術の界面から~ 1
渋谷区立松濤美術館学芸員光田由里さんと、デザイン事務所マッチアンドカンパニー主宰町口覚さんをお招きして、2010年9月3日に開催した百年「と」写真~写真と芸術の界面から~。
光田さんの著書「写真、『芸術』との界面に」で触れられている野島康三や安井仲治のいた1920代から、match and company新レーベル「M/light レーベル」が扱う田村彰英や大辻清司が活躍した1960年~70年代を経て、現在へ。写真と写真家の歴史、影響を受けた時代や写真家について語って頂いた2時間を、ほぼ全て文字にしました。全部で3回にわけ、順次公開していきます。
町口・俺の場合は写真よりも写真集が好きなので、写真集との出会いが最初なんですけど、子供のころ最初に「うわ、この写真集すげえな」と思ったのは、リチャード・アヴェドンの「ナッシング・パーソナル」なんですよ。アメリカの写真家から入ってるので。日本だって先人が良い写真集を出して、本当に世界に誇れる文化も日本にはあるんだけど、やっぱりアメリカ、欧米から入っていると最初の頃は欧米の写真家とか写真集に興味があって、それを徹底的にやっていったという経過があります。要するにあれです、ストーンズ好きになって、マディ・ウォーターズを聴くみたいな、ロバート・ジョンソン聴くみたいなノリで。やっぱりリチャード・アヴェドンから入ってると、日本の写真家は最初の方はあまり勉強しなくて。勉強し始めてもやっぱり最初はVIVOとかあそこらへんの方から入ってるので、最初の方の1910年代とか1920年代とかはどっちかっていうとヨーロッパの方に、ノイエ・フォトグラフィー的な、ナジとか。あっちの方に興味がいっていて、結構(日本の1910年代は)スコーンと抜けてたというのがあったので、光田さんの写真の本はものすごく勉強になった。何が良いかっていうと時代背景がちゃんとそこに書かれているので、すごくリアリティがあるんです。その人がいた周りの社会みたいなものもちゃんと描かれているので。勉強させて頂きました。
光田・ありがとうございます。私は写真の専門教育を受けたとかじゃないんです。写真の専門家に思われることもあるんですが、絵の勉強をしたことはあっても写真の勉強を学校でしたことはないんです。なぜ写真が好きになったかというと、それは作品との出会いなんです。絵っていうのもやっぱり海外の巨匠の作品を見ることはあっても、意外に戦前の日本の絵はあまり見る機会がない。だから、そういう一般的な流れで絵が好きだから絵の勉強をしようっていうくらいだった。だから、いま町口さんがスコーンと抜けてたと仰ったような、私が主に研究している戦前の芸術写真というのは誰にとっても抜けていたんですよね。みんなから遠くに見られていたというか、そんなに大事にされてこなかった歴史が長いかもしれない。
町口・そうだよね。森山さんとかは一緒に仕事しているので、やっぱり仲治とかは入ってくる。でもそんなに接点がないよね。
光田・そうなんですよ。だから、私も全然知らなかったんですけれども、偶然の機会で野島康三の展示をいきなり担当することになった。何も知らないのに。
町口・いきなり?それがいつですか?
光田・それがもう今を去ること十数年前くらい。そのときに、初めて野島さんの写真作品を見たんです。(作品を)見る機会がそんなにある人じゃない。私は、去年野島康三の写真展をもう一度担当して「作品と資料集」をまとめ、赤々舎から野島康三の写真集を出しました。
町口・作品と資料集?
光田・これはカタログ代わりに勝手に作っちゃったんです。中身は作品がちょっとで野島の日記とか原稿の下書きとか野島宛の手紙とか、そういうのを全部復刻しちゃったんです。野島さんに興味を持って研究してくれる人がいたら、これ使ってもらいたいっていう一心で。私がこれまでに集めた資料を全部復刻したんです。(野島康三の写真集は)去年出したんですけど、それを見て知らなかったことに出会ったら使ってほしい。野島さんの写真っていうのは私にとってぱっと見て「なるほど」っていう感じではなかった。「これなに?」って感じ。
町口・どこでそんなに野島さんにのめり込むことになったの?
光田・それがわからない。まず、インフォメーションも非常に少なかったし、知ろうと思っても解説書みたいなものはない。作品が一種異様だった、私が日頃思っているような写真とは相当違った。
町口・そこらへんの違いってなんなんですか?どこら辺の写真と比べて?
光田・つまり写真ってすごく広いんですけど、例えばコマーシャルっぽかったり、カレンダーになるような写真とはあまりに違った。それが何なのか、ということを知ろうと思って十数年いろいろやってみたんですけど、わからないですね。例えば、この赤々舎の写真集にも入っている肖像連作、謎の女性を撮って、「モデルF」って写真の裏に書いてある。だから、例えば藤原さんとか藤岡さんとかFがつくひとじゃないかなとか、でもいくら調べても彼女のことはまったくわからなかった。時々通ってたひとで職業モデルではなかった、野島さんと二人でアトリエこもってなかなか出てこなかった、というのが私がおじいさんたちに聞いた話です。でも、そういうことがわかったからといって写真がわかるわけじゃない。これは何か、っていうことがわからない、だけど知りたい。それでできるだけ調べるっていうことをはじめた。
町口・おじいさんが言っていたっていうのは、野島さんとお付き合いがあった人のとこへコンコンって行って、すいませんって、野島の話聞かせてくださいってこと?
光田・そうそう。私が研究始めたころは、ぎりぎり明治生まれの人の話が聞けた。今はちょっと明治生まれの人の話を聞くのは難しいけど、大正生まれの人の話なんかは聞けますね。1930年代に子供だった人とか。当時は色々な話を聞けた。
町口・本当に最後にやらなきゃいけないことをやったんだ。これ逃したらちょっとああいう本とか、ひょっとしたらないかもしれない。
光田・つまり、(野島康三に)会ったことのある人に会うということ。その人が持っているアルバムに野島が写っていたり、その人が引き出しから出してくれた中に野島からの手紙があったり、そういうのを辿り辿って資料集を作った。でも、だからといって写真がわかるわけじゃない。だけど、わかりたいと思ったときにできるだけ情報を集めて、もういっぺんまた写真に戻っていく。そういう感じが私の今までやってきたことなんです。
町口・じゃあ、松涛美術館で偶然野島さんの展示を担当したのが出会いなんだ。
光田・そう、それが近代写真との出会いでしたね。一人を研究することによってその人と同時代の色々な人のことがわかってくる。それを一人ずつ、野島さんの友達で良い写真家だなという人を順番に研究してきたという感じですね。それで一回りして、野島生誕120年で何かわかればいいなと思ったんですね。で、謎があるということがわかった。つまり、写真をわかるっていうことはどういうことかっていうことですよね。でも、町口さんが仰ってくれたように知られていないけれど良い写真があるということは確信したので、少なくとも数人は興味持ってくれる人がいるはずだと思いました。だから、その数人の人に届くようにやりたいっていう感覚です。
町口・まあ、光田さんがいなかったらこういうのもなかったんじゃない?
光田・(笑)忘れられちゃいけないような仕事はたくさんあるんですけど、見る機会や知る機会が非常に限られているために、いま写真に興味がある人がたくさんいて、アヴェドンだったらすぐアクセスできても、野島康三だと極端に通路が狭くなっちゃう。それはもったいないことで、いま写真やろうと思う人が自分の地続きのところに良いものがあるということに気づいてもらえたらいいなと思う。
町口・俺もね、写真集好きなんだけど、仕事はグラフィック・デザインなんですよ。自分も先人のグラフィック・デザイナーとかいるじゃないですか。仕事やってて思うんですけど、やっぱりバトンなんですよね。バトンが渡されていくっていう。日本ってやっぱものすごくクリエイティブな国で、俺がグラフィック・デザインやってて最初の一番すごいグラフィック・デザイナーって誰かなっていうと、俺の中では尾形光琳なんですよ。やっぱり光琳がプレスしているモノとか見てると、これデザインっぽいなあって感じて、そこから脈々とバトンが繋がってきて。だから、写真集は好きだけど写真が好きだとかいうわけじゃない。写真が好きというよりも、写真集。いわゆる印刷物がすごい好きで、だからデザイナーやってる。デザインの方でもバトンの受け渡し方とかは結構勉強したんですよ。写真家の方はあんま勉強してなくて。例えばだけど、今だともう70年代の写真家とか結構無視だよね。
光田・勿体ないですよね!
町口・あのさ、森山荒木とかあってさ、俺が一緒にやっているような世代があって。で、その間の70年代の作家とかも結構ものすごいのに。まるでいないかのようにさ(笑)。写真集出ないし。だから、そこらへんもあるのに、1910年代とか1920年代とか。ちょうど森山さんが生まれたのが1930年代。そこにはもはやもう写真というのはあるわけじゃないですか。そういう意味では、俺にとってこの本はバトンていうか。たかが写真なんて100年くらいなわけだから、別に江戸時代までいかなくていいわけじゃないですか。(光田さんの著書に)線引きまくりましたよ、俺。
光田・(笑)今のバトンっていうお話はすごく良いお話だと思うんですね。例えば野島とかは生前に写真集を全然出してないんです。プリントを作るっていうことが彼にとっての作品なわけだから、それを展示して見てもらうっていうそういうタイプのコミュニケーションですよね。すると、見る人ってすごく限られているけれど、ずっと覚えている人も確実にいて。私のすごく好きな写真家に安井仲治っているんですけど、安井なんかは野島のポートレイトが良かったっていうのをずっと覚えていた。あとは野島の友達の福原信三。彼なんかも戦前、1920年代はずっとアヴァンギャルドなんですね、これから新しい写真をやるっていってアヴァンギャルド運動を始めた。そこからたくさんの人が巣立っていって、その後に福原さん一派はすごく大きくなっちゃって、保守になったような見られ方もある。でも、その元はアヴァンギャルドだった、今までのものを否定して新しいものを作ろうとした。だから、現代の作家活動している人も、今までの古いことを否定しようとして新しいことをやろうとするじゃないですか。思うんだけど、それを思ったのは別にあなたが始めてじゃないっていう。江戸時代だって、尾形光琳だって、今までとは違うことをやろうとしてたわけで。
町口・VS狩野派とかね(笑)。
光田・そう(笑)。例えば福原新三さんなんかはパリから帰ってきて、日本の古い写真は非常に閉塞的だと、そこで新しい運動を立ち上げたら、大ブームになって支部とかできちゃって保守化していく。その頃には安井仲治が出てきていて、そういう良いところを受け継ぎながらもまったく新しいことをやるということに着手していくんですよね。その当時だってものすごく有名だったわけではなくて、一部の場所でだけ行われていた話なんですけども、でも出来ている作品はすごく素晴らしい。それでもし新しいことを何か始めようと思ったら、探してでもアクセスして、そのバトンを持つという意識で繋げていったらいいと思うんですよ。
町口・よくさあ、新しい写真とかいうじゃない。これは見たことないなあとか言っても見たことあるわけでさ。だから、いつも言ってるのは、もう全部やってんだからさ、先人がやってきたことをしっかり勉強しとけよっていう。うちのデザイナーにもよく言ってる、往々にしてそこに答えがある。それを今の時代にどうするかっていうだけの話だからさ。やっぱそういうものをしっかり勉強して、自分の身体のなかに入れて出せば、それは新しいっていうくらいで考えてないとやってらんないっていうか。そういう意味でいうと、俺にとってこの本(光田さんの著書)は、「名前ぐらいはねえ」とか、「あの人が好きだって言ってたなあ」という作家についてここまで書かれた本は今までなかったから、俺あんま勉強好きじゃないんだけど勉強しましたよ。これ皆さん読みました?難しくないですよ。
そうか、光田さん野島に惚れたんだ。
光田・尽くしましたよ(笑)。でも、やっぱりそれは作品が良いからなんですよ。作品の力です。だから、良いと思ってくれる人が他にもいるはずだから、そのために何かしたいっていう感じですね。
町口・野島さんと出会って、次にどこへ行くんですか?
光田・あてどない旅ではありますが、結局良いと思う作品のためにしか労働ができないので、良いと思う人や作品との出会いが繋がっていくということなんですけど。何を良いと思うかというと難しい問題だけど、彼らはこういう風なものをやるというような土台のあるところではやっていないんですよね。写真が作品だとか、それを売買するといったインフラがまったくない時代だったんで。土台がゆるゆるなところで、自分の立ち位置を作ってから自分がそこに立って作品を作らないといけない。そのことが一番重要なんじゃないかなと最近思います。例えばこれが素晴らしいデザインだというフィールドがあるとして、このフィールドで僕頑張ろうとかでなくて、これがデザインかわからないとか、これは写真だけど写真の王道ではないかもしれないとか、みんなから注目されるフィールドじゃないとか、だけどそこに行ってこんな扉を開けてしまったみたいな、そういうひとたちなんですよ。自分は一体何をするかっていう時、こっちの方向がいいとかそういうのはわからない、これが一番のクオリティだとかそういう方向はないわけですよ。どんな風に発表するか、誰とどんな風にコミュニケーションするか、そこからまず作っていってやっていく人たち。だから、町口さんがされているようなことも似てると思うんです。
町口・そう。俺も読んでて、俺と似てるなあとか思って(笑)。
光田・そうなんですね。町口さんのこの格好良さってそれなんだと思うんですよね。例えば、日展みたいなところで国のお墨付があるとか、この中で偉くなったら絶対文学賞だみたいな、そういうフィールドで頑張ろうっていうやり方もありますけど、フィールドなのかもわからないところに場所を作っちゃって、そこからやってるっていうことが何かを作るということの根本だと思うんです。だから、見たことのない扉を開けてしまって、こんなところからも光は射すんですかっていう。
町口・それもはやデザインだもんね。何もないところで、ぱっとやってさ。光が射してきたらそれはもう良いデザインだよね。
光田・町口さんにとっては良いデザインで、私にとっては良い作品なんでしょうね。例えば野島のような人は自分で画廊を作ったり、自分で光画っていう雑誌を作ったりもするんですけど、光画なんかも結構大判で、今までは展覧会とかで作品を掛けていたけれど印刷でダイレクトに届けられないかっていうことで始まった雑誌なんですね。聞いたら本屋には全然並ばないような雑誌だったらしくて、当時の色々なひとに聞いたけど本屋で見たことないって。例えば、光画の同人の木村伊兵衛は頼まれて仕事をする人ですよね。こういう感じの美人の写真をお願いしますって言われたらバシッと撮る人ですよ。でも、美人じゃなくてもすごい写真を木村伊兵衛が撮っているかっていうと・・・。美人とか関係なくって、(重要なのは)誰にも求められていない未開拓のフィールドですよ。私が好きな写真家って結構ポートレートを撮っている人が多くて、例えば風景写真には自分の気持ちが託しやすかったり、静物写真だと自分の思ったようにアレンジできますよね。だけど、人間が一番作品になりにくい。そこから新しい世界を開いている人に興味がありますね。
町口・なるほど。野島の話は飲んだら朝までになるんだろうね。
光田・そうですね、長くやってますから(笑)。色々なことはわかったんですよ、例えば何月何日に大体何をしたとかいうことも大体わかった。だけど、それがわかったからといって写真がわからないっていうそこがまた良いですよね。
町口・やっぱり野島の写真は「謎」なんですか?
光田・そうですね、一種のディスコミュニケーションがあるような。例えば類型的な労働者の顔とか、母性的な顔とか、そういうものだったら自分がどう対していいかわかるんですけど、野島の人物は類型的になっていないので一種非人間的なものを感じる。「自分」を入れられない。例えば、展覧会なんかに行くと色々な絵があって、これは全部この人の自画像だなみたいな展覧会ってありますよね。野島の場合は、非自画像的なんですよ。自分じゃないものを求めている人なんです。だから、これはこうだなっていう風に答えが出ないんじゃないのかな。
町口・(野島に)近い方っていると思います?まあ、失礼な話かもだけど。
光田・いないです。海外の作家とかでもちょっといないので、一種異様な感じがする作家ですよね。