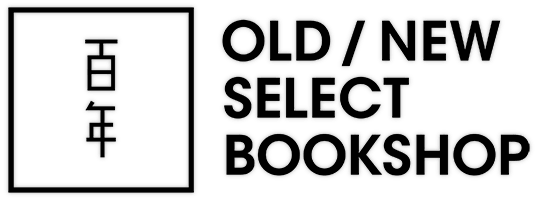桜井鈴茂
ロッキング・オンのライターになりたかった!?
―― いま、小説の原体験の話をしましたけど、その後は、音楽に行くんですよね。
桜井■というか、音楽のほうが先で、中二から中三にかけてバンドを組んでました。中学の文化祭に個人発表っていうコーナーがあったの。クラスの出し物……演劇とか合唱とかが終わって、閉会式の前に。そこで、三年生の男子がバンドを組んで演奏する、みたいなのが、なかば伝統のようになってた。中一の時にそれを見て、おれも三年生になったら、やろうと。だから、音楽のほうが早いです。高一のときもバンドはやったし。
―― バスケをやりながら?
桜井■やりながら、というか、文化祭向けにね。バスケ部に一人、音楽好きがいて……あ、そいつがあれだよ、『蛍、その他短編』を無理やり貸してきたやつ。そいつに誘われて、バスケ部の練習をサボって。で、文化祭が終わった時に、そいつに「おれはバスケやめて、本気でバンドやるから、おまえもいっしょにやらない?」みたいなかんじで誘われたんだけどね。あそこで、バンドを選んでいたら、だいぶ違ってたかもね。でも、そのころ、バスケ部をやめていくやつが続出してたの、練習がキツいとか、勉強しなくちゃとか、遊びたいとか、さまざまな理由で。そのバスケ部をやめていく流れに、なんでか乗じたくなくて、バスケを続けたんだよね。
―― 楽器のパートは?
桜井■ベース。中学の時にじゃんけんで負けて、ベース。ほら、中学の時は、みんなが楽器を持つの、ほとんどはじめてだったから、まずは担当を決めたんだけど、ひとり農家の息子がいて、そいつんちの納屋で練習することになったから、そいつがドラム。ドラムセットを持ち運ぶ必要ないから。女の子がひとりいて、その子がキーボード。そこまでは異議なし。で、あと男が三人。二人がギターで、残りがベース。みんなギターをやりたくて、じゃんけん。おれ、じゃんけんは弱いから(笑)。
―― やりたかったの?ギター。
桜井■だって、かっこいいじゃん!
―― まあそうですよね、一番モテるもんね。
桜井■今になってみるとベースもかっこいいけどさ。その時はまだ中学生だもん。その流れで、高校の時もベース。いまいち楽しさがわかんないままだったなあ。部屋で一人で練習しても、ボンボンいってるだけだし。耳コピーする時も、聴き取りにくいし。うん、だから、じゃんけんに勝ってギターをやってたら、バスケはやめてバンドを選んだかもしれないね。
―― 高校生でなかなかベースを評価できるやついないでしょう。
桜井■うちの母親には言われたけど、ベースが一番かっこいいって。縁の下の力持ち的な? でも、おれは、どう考えても、縁の下の力持ち的なキャラじゃない(笑)。
―― でも、バンドはそれっきりではないですよね?
桜井■大学三年になってまた始める。その前に……高校のバンドなんだけど、おれがやめた後に、他校のベーシストを入れたりして、三年の時に、ヤマハのポプコンの全国大会にまで進んだんだ。友達だから、もちろん応援はしてたけど、心のどっかに、あの時やめないでおれもやってたら、みたいなのがあるじゃん。軽い後悔が。だから、大学に入ってからも、当時はやっぱり音楽が一番好きだったけど、いまさらバンドは、という気持ちが働く。それに楽器もベースだし(笑)。一方、小説を読むのも好きで、文章書くのも嫌いじゃなかった。音楽が大好き、文章書くのもなんとなく得意。この二つを合わせたら、何?
―― 詩を書く、でしょ。
桜井■いや、音楽ライターでしょ!
―― 音楽ライターなんだ。
桜井■ロッキング・オンの編集者とか。大学一年二年の時はなんとなく、ロッキング・オンのライターになりたいな、とかって思ってた。
ロンドン的な曇り空
―― 大学はどこでしたっけ?
桜井■明治学院っていう軟派な大学なんだけど。プチお嬢さまとかプチおぼっちゃまとかが来てるような学校。そんなところでも、ロッキング・オンはわりかし読まれてたと思う。おれ、大学に入ってからも、友達の付き合いでバスケのサークルに参加してたんだけど、練習の後にシャワー浴びながら、「ストーン・ローゼスいいよね」「おれはハピマンのほうが好きだな」みたいな話、してたもん。今、大学のバスケのサークルで「ストロークスいいよね」「いやいや、ヴァンパイヤ・ウィークエンドが」みたいな話、してるかな?
―― いや、してないでしょう。
桜井■おれらはしてたんだよね。もちろん、みんなじゃないけどさ。けど、とくべつ珍しいというわけではなかったと思う。まあ、ともあれ、大学二年の終わりまでは、そんなことを……音楽ライターになりたいなあ、みたいなことを、ぼんやり考えてた。……それで、二年と三年の間の春休みに、一人でロンドンとパリに行くんだけど……はじめての海外旅行にして、はじめての長い一人旅に。
―― それは、どうして?
桜井■大学に入った頃ってバブル絶頂期だからさ、六本木で合コンやったりして、チャラチャラ遊んでたんだけど……岡村靖幸の『カルアミルク』の世界だよ。“ファミコンやってディスコに行って、知らない女の子とレンタルのビデオ見てる~♪”っていう。おれはとくに、田舎から東京に出て来てるから、最初の一年かそこらは、そういう日々も楽しかったんだけど、やがてうんざりしてくるんだよね。というか、これ、どこへ向かってるの、って。酒を飲んでたいして中身のない話をして女の子といちゃついて……こんなことして、いったいおれはどこへ向かってるのって。音楽ライターになるにせよ何になるにせよ、もっと真剣に考えなきゃ、てことで、よっしゃロンドンとパリだ、と。今後、飲み会はぜんぶ断わるぞ、みたいな。それで、二年の夏以降、バイトの量を一気に増やして、ぜんぶは断れなかったけど飲み会にも極力出ないでお金を貯めて、次の春休みに、ひとり旅立った。ロンドンに二週間強、パリに二週間弱。ぜんぶで二十九泊三十日。
―― 語学は?
桜井■その時は、ハロー、サンキューのレベル(笑)。
―― 何学科だったんですか?
桜井■社会学科。語学は全然だったけど、海外へ行った経験がないから、日本語が通じないってことがどういう状況なのか、いまいちピンと来ていない。もう、勢いで行っちゃったんだよね。でも、めっちゃ楽しかった。あの一人旅が、我が人生においての、一番大きな岐路かもしれない。
―― 当時のロンドンはどんな感じでした?
桜井■音楽でいうと、セカンド・サマー・オヴ・ラヴとかマッドチェスター・ムーヴメントとかが終わりかけてたころじゃないかな。レイヴには行ってないけど、クラブには行った。もちろん、ギター・バンドも好きだから、ライヴハウスにも。毎晩どっちかに行ってたね。めっちゃ楽しかった、っていうのは、もちろんそのことだけじゃないんだけども。
―― 東京はまだディスコ?
桜井■クラブがぎりぎりかな? 始まってるクラブはあったかもしれないけど、まだメインはディスコだったはず。ジュリアナとか。ま、それを抜きにしてもさ、いろんなことが衝撃的だったよ。
―― 例えば?
桜井■例えば……そうだね……カフェとかレストランに入った時の、お客さんと従業員のフラットな関係性に、いたく感服した覚えがある。お互いの「サンキュー」に。上下がない「サンキュー」や「バイバイ」に。どっちかがへりくだってるんじゃなくてさ。日本は「お客様は神様」みたいなところがあるでしょ。金を払うほうが偉い、みたいなさ。時々、ゲロを吐きそうになるよ、日本のお店での関係性に。
―― いまは日本でも増えてきてますよね。うちの店も、そういうのがあって、出て行くときに「ありがとう」って向こうが言ってくれたりする。
桜井■日本も少しは変わってきてるってこと?
―― うん、変わってきてる。
桜井■でも、逆の流れもあるでしょ。スタッフがひたすら客にかしずく、みたいな。何を言っても、申し訳ありません、からしか会話が始まらないという。客もふんぞり返って、ありがとうさえ言わない。
―― それを変えたいなー、と思って。
桜井■それは本当に大切なことだと思う。
―― 桜井さんとしては、イギリスに行って、そういう、客と従業員の関係性に衝撃を受けたと。
桜井■うん、受けた。というのもね、旅行費用を貯めるために、銀座の高級喫茶店で一年くらいバイトしてたんだけど、その時に、客の横柄さに、もちろん全員ではないけど、総じて、客の横柄さに、辟易してたの。スタッフのほうも、個性は捨ててやたらとへりくだるような教育を受けるじゃん。ようするに、奇妙な上下関係が発生するんだよね。なにこれ、変、ってずっと思ってた。で、ロンドンやパリに行ったら、それだもん、客もスタッフもお互いに、サンキュー/メルシー/プリーズ/シルヴプレ、の世界だもん。そういう場所に身を置いているだけで、なんか、気持ち良くてね。こっちでは、働いてる時も、個性を持ったひとりの人間でいられるんだなあ、って思った。あと、ライヴハウスでの客の反応の仕方もぜんぜん違ってて。日本だといまだにそういう側面は残ってると思うけど、音楽そのものに反応しない。演奏者が有名かどうか、自分の目当てかどうか、で反応してる、音そのものじゃなくて。有名なシンガーやバンドだと、たとえ悪い演奏してても、わ〜素敵〜ってかんじであるでしょ? 逆に無名の人だと、こんな人知らんって腕組んで傍観してたりして。じっさいはすっげえ音を鳴らしてるときでも。ところが、向こうだと、前座のバンドだろうと音楽さえ良かったら客は思い切り反応してて、時にはメインを食っちゃったりする。そういうのは、当時の日本のライヴハウスではなかなか経験できないことだったから。
―― 楽しみ方が違うわけですね。
桜井■うん。ま、そうやってロンドン、パリとひとりで旅をしてきて、帰ってきて大学三年。学友たちがそろそろ就職のことを考え始める時に、おれは無性にバンドがやりたくて。しかも、今度はベースじゃなくて、自分で曲を書いて歌いたくて。
―― やっぱり、ロンドン、パリの経験が大きかった?
桜井■ちょっと長い話になるけど……高校時代の同期の女子が当時、ロンドンのアートスクールに通っててね、最初の数日は彼女の部屋のソファに寝かせてもらったんだけど、彼女との会話も大きかった。共同のキッチンにさ、カミーユ・クローデルみたいな、作りかけの彫刻作品とか置いてあるわけ。あ、彼女ってうちの高校ではトップクラスの子で、現役で東京外語大と北大に合格してるのね。それで、北大に行ってるんだけど、一年もしないうちに学校やめて、ロンドンに渡って、アートスクールに通って、カミーユ・クローデルみたいなの作ってる(笑)。おれ、訊いたんだよ、「これでやっていけると思ったんだ?」って。そうしたら、怒ったように問い返されてさ、「やっていけるってどういう意味?」って。「やっていけるとかやっていけないとかどうでもいい。自分が何をやりたいか、わたしにはそれしか関係ない」って。あれはドキッとしたね。いつのまにか自分が打算的に物事を考えるようになってたことに気づかされた。というか、ふつうの大人になりかけてることに。もちろん、ふつうを目指してるんだったら、それでいいんだけどね。
―― なるほど。
桜井■それと、もう一つあってさ。カミーユ・クローデルの部屋を出て何日か経ったころに、カムデンロック・マーケットで、一つ上の女の子と知り合うんだ。知り合うっていうか、おれがナンパしたんだけど(笑)。いいかんじの女の子が向こうから歩いてきて……ほら、当時はおれ、英語はほとんどしゃべれないから、ナンパするとしたら日本人しかありえないんだけど……当時は携帯もないしネットもないから、一人旅を続けてるとだんだんコミュニケーションに飢えてくるの、それで、「ご飯食べませんか」って声をかけて。で、ご飯を食べながらいろいろと話したんだけど、その子はU2が好きで、それが高じてダブリンに短期留学してたとかで、その日の朝にロンドンに移ってきた、と。それじゃいっしょにライヴハウスに行こうってことになって、その晩から四日くらい連続して、行動をともにするの。夕方の六時くらいに待ち合わせて晩御飯を食べて、それからライヴハウスに行くっていうのを四日か五日連続で。で、翌日には彼女が日本に帰るっていう、まあ、最後の夜に……その時までには、おれ、彼女に恋心を抱いていて、そのせいもあって、大学生なりに真面目な話になったの。真面目な話をして、その流れで告白しよう、みたいな(笑)。
―― 向こうもそういう気になってたのかな?
桜井■いや、それはしらない(笑)。ま、とにかく、真面目な話をした。時期も時期だから、主に近い将来の話だよね。ライヴが終わってからバーみたいなところでギネスとかジントニックとか飲みながら。で、おれが「いずれはロッキング・オンとかのライターになりたいんだよ。それで、特派員とかになってこっちに住めたら最高だなあ」みたいなことを話したら、彼女の眼つきが俄然厳しくなってさ。「あんた、音楽が好きなんでしょ? なんで音楽が大好きなのに、自分ではやらずに、それを書く側にまわろうとすんの? 発想がひねくれてない?」って。「いや、だって、楽器、下手だし」っておれが言うと、今度は「じゃあ、歌えばいいじゃん。歌詞書いて自分で歌えばいいじゃん」って、お叱りを受けた(笑)。正直、怖かったね。怖くて告白できなくなっちゃったもん(笑)。……とまあ、そんな二つのエピソードがあって、日本に戻ってきて、さっそくバンドを始めた。
―― バンドのメンバーはどういうふうに?
桜井■最初は、大学のバンド系のサークルをまわって。ちょうど新入生勧誘の時期だったから。「おれ、三年なんでサークルに入りたいとかじゃないんだけど……ジョニー・マーみたいなギタリストを探してて」とかって触れ回って。「あ、それはおれのことだ」とか言うやつがいて……まあ、そいつとは結局、ライヴを一回しかやらなかったけど。あとは、音楽雑誌のメンバー募集欄を見て葉書を書いたり、自分でもメンバー募集の投稿したりして。レコード屋さんの掲示板とかにも貼ったし。まあ、メンバーに関してはいろいろと紆余曲折があったけど、そのまんまバンド活動に入っていくんだよね。就職活動なんか完全にほっぽり出して。それで、結局、二十七まで続けた。
―― 女性たちの言葉が今の今まで尾を引いてる、啓示というか。
桜井■もともと、おれはやりたいことしかできないタイプの人間なんだろうだけど、大学生になってそれなりに知恵がついてきてシンプルじゃない考え方を、ようするに、大人の考え方をするようになってたんだと思う。しかも、うちは勤め人の家庭だから、親たちがやりたいことをやって、おれを育てたんじゃないじゃん? もし……さっき見かけたから、例に出すけど……媒図かずおの息子だったら、ぜんぜんちがうと思うよ。うちは、おやじが農協の職員で、おふくろは保健所だよ。反発しながらも徐々に覚えてくじゃない、生きていくってどういうことなのかって。そういう時に、高校時代の同級生と会って、彼女は大学教授の娘なんだけどね、彼女のアパートの、でかい共同キッチンのテーブルに座って、窓ガラスの向こうに、いかにもロンドン的な、曇り空がぱーっと広がってて……そんなところでさ、「わたしは自分のやりたいことをやってるだけ」みたいなことをスパッと言われるとさ。その瞬間に、脳についてる“打算”のヒューズが飛んだもん、バチンって(笑)。
―― それで音楽を二十七歳までやったんだ。
桜井■やった。そして、挫折した(笑)。
そして『アレルヤ』へ
―― 『アレルヤ』を書いたのは何歳の時ですか?
桜井■三十二、三歳。そこまで行くには、まだ五、六年かかる。
―― その間はなにを?
桜井■バンドをやめて、いったんは札幌に戻るんだよね。その時には、最初の奥さんがいてね。彼女は東京の人だけど、「バンドやめたんだし、東京にいる必要ないんじゃない?」とかって言ってきて。彼女自身、北海道に対するあこがれみたいなのを持ってたんだけど。自然に恵まれた北海道で、ふつうの暮らしをしたいっていう。ちょっと複雑な環境で育った人だったから、なおさら。おれのほうは、ふつうの家庭で育ってるんで、ふつうの暮らしにあこがれどころか、幻滅さえ抱いているんだけど……でもまあ、彼女がそう言うんだったら、それも悪くないか、と。それで、札幌に引っ越して、郵便局で非常勤の配達員として働き始めるんだけど……いずれは試験を受けて正規の職員になるつもりでね。ところが二か月も経たないうちに、もうイヤになって。郵便局で黙々と労働をこなして、子どもを二人か三人作って、日曜日は家族で動物園へ……みたいな生活は、おれには申し訳ないけど無理だわって。まあ、そんなこんなもあって、もちろんそれだけじゃないけど、彼女とは離婚しちゃうんだ。それで、実家に戻って、出戻り状態が一年くらいかな。それから、京都に行くんだよね。まだ、小説書こうとは思ってない。
―― なんで京都だったんですか?
桜井■最初はね、イギリスかアイルランドに留学しようと思ってたんだよね。先のことはともかく、一度向こうで暮らして、ちゃんと英語を身につけたいと思って。でも、そのとき、すでに二十八とかだから、親には頼めないわけ、イギリスに行くから八百万出してくれ、とは。それで、ひとまず貯金をはじめたんだけど、あるとき冷静に計算したの、郵便局で非常勤職員として週に六日働いて、ぎりぎりまで倹約して月にこれくらいは貯金して……って。そうすっと、イギリスかアイルランドの小さな町で学校に通いながら丸二年間住む金を貯めるのに、最低でも七年とかかかる。まあ、少々は親に泣きつくにしても、五年だと。五年間は郵便配達を続けなくちゃいけない。たった一週間でも死にそうな思いをしてるのに、五年かあ……しかも、そのときには三十三歳とかになってる……だめだ、こりゃ、おれには無理だ(笑)、と。そんな時に、大学生のころに流れてたJR東海のコマーシャルのコピーを、ふいに思い出すの。「そうだ、京都に行こう」(笑)。いや、マジで(笑)。
―― (笑)。京都には何がありましたか?
桜井■……一言では答えられないけど、楽しく充実した二年半だったよ。
―― 何をしてたんですか?
桜井■はじめのうちは、祇園のスナックでボーイをやったり、ほんやら堂っていう学生街の食堂みたいなところで働いたり。それから、おばんざい料理店……まあ、ちょっと粋な居酒屋の、オープニングからの店長を。そこはまあ、母親のいとこにあたるおばさん夫婦が経営者で、おれが京都に越した時は、まだオープン準備中だったんだけど。バイトをさせてもらうつもりでいたら、ある朝、おばさんがわざわざ部屋までやって来てね、「店長として、お店全体のプロデュースから、バイトさんのコントロールまでやってほしい」って言われて。それからオープンまでの二か月あまりは、設計士と内装の最終打ち合わせをしたり、メニューを考えたり、バイトの面接をやったり、と大わらわだった。
―― 楽しかったですか?
桜井■うん、楽しかった! お店が始まってからもしばらくは楽しかったよ。好きな音楽をかけられたし。レナード・コーエンがかかってるおばんざい料理屋は、京都でもそこしかなかったと思う(笑)。でも、そのうち、毎日毎日、お店に立つのがつらくなってきて。お店ってたとえお客さんが来なくても閉められないわけじゃん? 毎日、午後三時から深夜まで働いて……そのあと、ひとりで飲みに行って、こんなんでいいのかあ、って考えちゃったもん。こうやっておれは歳をとっていくのかなあって。
―― 続かないな(笑)。
桜井■ねえ(笑)。でまあ、そんな頃に、今の奥さんと出会うんだよね。お店のカウンター越しに。つまり、お客さんだったんだけど。彼女は当時、京都のメーカーでデザインの仕事をしてたのね。それで、飲みに行っていろんな話をしたんだけど、彼女が「いずれは独立したいと思ってる。でも、経営のこととかお金のこととか、考えるだけでうんざりしちゃう」とかって言うわけ。その時に……その時には彼女のこと、好きになり始めてるわけだけど(笑)、あそっかっておれは思うのよ。あそっか、じゃあ、彼女がうんざりする経営のことをおれがやればいいんだって。安直にも(笑)。それで、休みの日に、ジュンク堂に行って、社会人のための大学院入学案内、みたいな本を手に取る。その本で、同志社の大学院に、起業を目指している人のためのコースが設置されていることを知って。あ、これじゃん(笑)って。それで、二週間くらい猛勉強して、そこに入学しました。
―― その時、桜井さんはいくつ?
桜井■1999年だから、三十か。入学してすぐに三十一。でまあ、最初の一年は、まじめに勉強します。まじめに勉強しますが、一方で、自分が商売向きじゃないことを徐々に認識する。商学研究科のベンチャービジネスという専攻なんだけど、同期が六人ほどいて、内三人は、修士号をとるためにベンチャービジネス論をやりたい人で、おれを含めた残り三人が起業を目指してた。でも、彼らって、もともと商売やってる家の娘と息子なんだよね。おれみたいに、勤め人の息子じゃなくて。小さい時から自分で商売をする思考になってるわけ。彼らとしゃべってると、こりゃあかなわないわって感じた。そんなことを感じつつ一年が過ぎたころに、すでに同棲してた、今の奥さんと籍を入れることになって、新婚旅行でキューバに行くのね。おれは当時、ほとんど文無し状態なんで、行けてもせいぜいが熱海とかなんだけど、奥さんが条件付きで、お金出すからって言ってきて。それが、へんな条件でね。新婚旅行を文章でまとめて欲しいって(笑)。
―― 文章で?
桜井■うん。なんかね、彼女は海外出張によく行ってたんだけど、付き合い始めて最初のアメリカ出張の時に、おれ、ラブレターを書いて、ホテルにFAXで送ってたんだ、まだコンピュータは持ってなかったんで。その、ラブレターの文章にピンと来てたんだってさ。うちの奥さん、中学や高校の時は、自称だけど、文学少女だったらしくて、谷崎とか三島とか大好きなのよ。ピンと来たって言ってるよ、この人作家になるかもしれないって。だから、長い文章を書かせようという魂胆があったらしい(笑)。そんなわけで、新婚旅行を文章でまとめろと。おれはおれで、そんなんでキューバに行くお金を出してくれるんだ、楽勝!って思ってさ。旅行中、メモをとりまくったもん。朝も彼女より早起きして、メモをもとに断片を書いたりして。それで、帰国してからせっせとワードに書いていくわけ、大学院の勉強なんかほっぽり出して。どうせなら、他人が読んでも面白いものにしようと思って、それこそ、村上春樹やポール・セローの旅行記みたいに。結局、三百枚を越えたかな、たった十日間の旅行なのに。
―― それはどうしたんですか?
桜井■すごくがんばって書いたし、なかなかのものが書き上がったという自負も少なからずあったんで、どこかで出版してもらえないかなあ、と思ったんだけど、よく考えたら、村上春樹の旅行記が出版されてるのは、彼が小説家だからじゃん? あるいは有名人だからじゃん? 一方、おれはただのしがない大学院生じゃん。そんなやつの旅行記が商業出版されるわけないじゃんねえ。愕然。というか、当たり前だけど。旅行記を商業出版してもらうためには、まずは小説家になるしかないんだなあって……はじめて、小説を書くことを意識するんだよね。それで、大学院生が終わりかけの時に、もちろん、修士論文なんてほっぽり出して、『アレルヤ』を書き始める。やっと、繋がったね(笑)。長い話で申し訳ない(笑)。
―― 長い道のりでしたね。
桜井■長いし、遠回りしてるよね。
―― 多少、切羽詰った感じもあったのかな?
桜井■あったよ。奥さんにも「あと、数カ月で大学院が終わるけど、どうするの? 今までは一応、わたしが養ってきたけど、いつまでも無理だよ。どうにかしてもらわないと」って言われてたしね。おれは「ちょっと待ってくれ。小説書くから」って。それで、早起きの苦手なおれが、毎朝早起きして書いたのが、『アレルヤ』。
―― で、見事「トリッパー」に。
桜井■「トリッパー」に送ったのは間違いだったかもね(笑)。最初はね、タイトル違ってるかもしれないけど、三月末が締め切りの「すばる」に出してるの。三月が奨学金給付の最後だったから、それまでに大急ぎで仕上げて。でも、一次審査しか通らなかったんだよね。けど、おれとしては、手応えがあったから、もう一度じっくり改稿しようと思って。このまま眠らせておくわけにはいかない!って。それで、秋にひと月かけて、改稿、というより、リライトするんだ。十月末の締め切りが、「群像」と「トリッパー」。「群像」に応募すべきだったんだろうけど、「群像」は二五〇枚以内という応募要項だった。「アレルヤ」は数えてみると、二八七枚だったかな。今になって思えば、そのくらいどうってことないのかもしれないけど、当時はそのへん馬鹿正直に考えてたから。それに、群像の賞金が五十万で、トリッパーが百万。ヒモ状態の当時のおれには、この五十万の差は異様にデカかった。そんなわけで、トリッパーに。その時には確信があったね。これは絶対いけるって。
―― うん、あれはよかった。傑作じゃないですか。
桜井■書いてる途中……そうね、百枚過ぎたあたりかな、小説を書くことがおれの仕事なんだって確信するのは。これまでの人生ってのは小説を書くための準備期間だったんだって。おめでたい話だけど(笑)。でもまあ、二十七でバンドをやめてからは、なによりも小説を読むことを拠り所に生きてきたからね。離婚して実家に戻って非常勤職員として郵便配達をしてる時も、京都のおばんざい料理屋で店長をしてる時も、彼女、というか後の妻に養われながら大学院に通ってる時も。それが、ようやく形となって現れたってことなんだろうな。
―― そこらへんの経験が大きく小説にも出ていますよね。実際、ぼくは『アレルヤ』から入ったんだけど、その時にも思ったし、それこそ主人公に鈴茂さんが反映されてるというか、やっぱり共感できた点があったからこそ、はまったんだと思う。
桜井■そういうふうに言ってくれる、樽本くんみたいな編集者があと三人いたら、おれの状況もだいぶ違うと思うなあ(笑)。