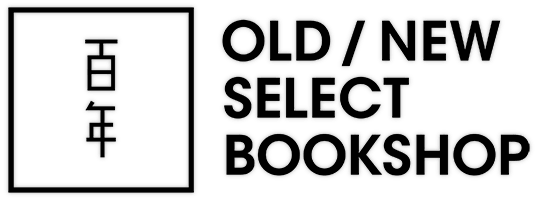「サウダーヂ」から離れて

平日の午後、渋谷で『サウダーヂ』という映画を観ていて、何とも不思議な気持ちにさせられた。山梨を舞台にした、この映画に心を動かされたというわけではない。多くを取り込もうとするあまり、構成の粗さが目立ってしまっている点は残念だと思うし、いささか短絡的な主題の導き方には、やっぱり賛同できないのだけれど、それでも、語尾に「だら」とか「ら」をつけて交わされる会話や、団地のなかを歩く日系ブラジル人の姿を映した場面には、ぐっと胸を掴まれる思いがした。そうそう、こんなふうだった、こんな場所にいたんだった、そう思った。
“昨日、駅まえでずっと待ってたさあ。でもあそこ、やたら寒いわけ”
“ほんと、こいつ、うけるら”
“そうだら、普通、そんなことしねえら”
『サウダーヂ』の舞台となっている甲府市と同じく、私が育った静岡県の東部、御殿場市でも、こんな言葉遣いをする。それは、中部地方に属していながら、県庁である静岡や浜松より、隣接する神奈川や山梨のほうが距離的に近いことも関係しているのだろう、名古屋よりは関東に近いアクセントで、そして、だからこそたとえば東京に行ったとたん、あっという間に霧散してしまう話し方で、私は少年時代、友人たちと言葉を交わしていた。
また、いまではすっかり減ってしまったけれど、私が子どもだった頃には近所にたくさんの田んぼがあり、少し自転車を走らせればハヤやウグイといった魚を釣ることのできる川があって、放課後、校庭でボールを蹴ったり、誰かの家でテレビゲームをしたりしないときには、日が暮れるまで自然のなかで遊ぶこともできた。
そんな片田舎の学校に日系ブラジル人の転校生がやってきたのは、確か小学校の高学年から中学校の入学時期だったと思う。時代的に言えば、日本経済が活況を呈していたころ、いわゆるバブル期にあたるのかもしれない。恐らく、彼らの両親が市内にあった自動車部品工場、あるいは工業団地と呼ばれる地区に仕事を求めて移住してきたのだろう、数人の日系ブラジル人がクラスメイトとなり、教室で机を並べることとなった。
最初、担任の教師から、彼らがブラジルから来たのだという説明をされた憶えもあるが、週末に駅まえで見かける、キャンプ富士のアメリカ人海兵がもっとも身近な「外国」であった当時の私にとって、その説明はピンとくるものではなかった。外見的にとりたてて大きな違いがなく、そしてまた「日本風の名字に、外国風の名」を持つ彼らの名前に混乱してしまったせいか、日系という言葉の意味をほとんど何も理解できないままでいた。いま考えるとほんとうに情けないけれど、当時は彼らのことを、父親か母親の片方が外国の人、そんなふうにしか思っていなかった。
日本語に不自由していたこともあって、彼らは日々の授業やブラジルとは異なる学校の慣習に困惑していたものの、クラスのなかで孤立したり、誰かと決定的な対立をしたりすることはなかったように記憶している。もちろん、教室の至るところで喧嘩やいざこざは絶えず起こっていたけれど、その大半は相手の出自や人種的な違いによるものではなく、子どもが数人集まればどうしたって生じるもの、つまらない意地の張り合いだとか一方的な思い込み、あるいは互いに我を通そうとするときに引き起こされる、他愛もないものがほとんどだった。
とはいえ、あくまでそれは日本人である私の印象であるから、あまり当てにはならないだろう。自分の意思とは無関係に生まれ育った土地を離れ、言葉の通じない場所で日々を送らなければなかった彼らにしてみれば、毎日は憂鬱で、苦痛に満ちたものであったのかもしれないのだから。何ひとつ分かっていなかった、という表現さえ当てはまる自分に、当時の彼らの心境について語る資格など、あるはずもないのだから。
高校卒業と同時に実家を離れてしまったため、私は日系ブラジル人のクラスメイトたちのその後を知らない。ただ、それから二十年近い時間が過ぎる過程で、彼らの存在は少しずつ私たちの周囲に浸透していった。
現在、市によって指定されているゴミ袋には、日本語の他に数種類の言語で説明が表記され、市役所の広報もポルトガル語版が出されている。一時的とはいえ、商店街のなかに日系ブラジル人向けの雑貨屋やシュラスコ店ができ、いまではスーパーやショッピングセンターでブラジル代表の鮮やかなユニホームを着ている子どもを見かけることもめずらしくなくない。
人口の集中する都市部とは違った、地方の町にとって、そうした変化が最初の一歩であるとしたら、次の歩みはどんなものになるのか。郷愁を表すと同時に、ある人の不在や大切なものを失ったときの悲しみの意味を持つ「サウダーヂ」という一語に何もかも委ねてしまうのではなく、そこから洩れ落ちてしまったものまで、きちんと自分の目で見届けたい。