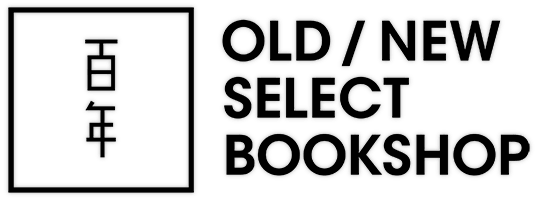ミステリーズ 運命のリスボン/ラウル・ルイス レビュー
少年には名前がひとつしかなかった。修道院で共同生活をしている他の子どもたちは、父方と母方の姓を受け継いでいるのに、少年にはたったひとつの名前しか言い渡されていなかった。ただのジョアン。彼の名前は、ジョアン。それ以上でも、それ以下でもなかった。まず、それが最初の秘密となる。どうして自分は他の人と違っているのか。ほんとうの父は、母は、どこにいるのだろう? 少年がみずからの両親を意識することから映画は始まり、その疑問は長らく会うことが許されなかった母、そして、育ての親でもある神父の口から解き明かされる。
4時間26分という大長編の映画は、当然ながらそれだけでは終わらない。母や神父はもちろんのこと、父の命を奪った無法者や神父のことをよく知る老修道士、そして成長した少年を惑わす公爵夫人といった人物まで、それぞれの背景が明らかにされていく。少年を知ることは、彼を取り巻くすべての人を知ることであり、それを抜きにして現在を語ることなどできない、といった具合に。
原作を書いたのは、ポルトガルのロマン主義の先駆者といわれるカミーロ・カステロ・ブランコ(映画さながら、作者自身も私生児として生まれ、姦通罪などで二度の投獄を経験しながら、その生涯で260を超える作品を残したという点も見逃せない)。
19世紀後半のポルトガルを舞台に、修道院や貴族の屋敷、それにコルク林を走る馬車のなかで、着飾った男女が言葉を交わし、みずからの過去に思いをめぐらせる。いさかいは一対一の決闘で解決する、といったことがまだ当たり前だった時代の物語だ。
映画を観おわったあと、最初に思ったのは、秘密が秘密にならないということの不思議さだった。原題に従えば、リスボンの謎。けれども、この映画のなかでは謎解きの要素は極力控えられ、登場人物の過去ばかりがしつこいくらい丁寧に語られている。もちろん、これは映画なのだから、コマとコマ、カットとカットのあいだには底知れない空白が広がっているはずなのだけれど、通常、その隙間を巧みに組み替え、時間のあいだに落ち込んでいる出来事を見え隠れさせることで、観る人の好奇心を煽るのに対して、ここではそうしたサスペンスの要素が第一とは考えられていない。映画の長さも関係しているのかもしれないが、登場人物が抱えている背景は、すぐ さま、もしくは先延ばしすることなく説明され、語りつくされている。秘密よりも、その人となりを物語ることに重点がおかれていると言ってもいいだろう。映画が展開していくなかで、点と点のどれも繋がっていることに気づかされはするものの、それがさほど重要とは思えない作りになっている。
と、そんなことを考えていたら、週に一度、語学を習っているポルトガル人の先生が以前に言っていたことを思い出した。ポルトガルでは、結婚すると、ファーストネームに洗礼名、それに母方の名字と父方の名字を並記する習慣があるという。ただし、表記する名前の数に厳密な決まりはなく、結果、恐ろしく長い名を持つ人がいるのだと。
最初に名前をひとつしか持たなかった少年が登場し、その後、彼にまつわる人の過去が順々に重ねられていく。いたってシンプルに時間の処理が施されているこの映画と彼の国の習慣を結びつけて考えたくなるのはわたしだけだろうか。
ミステリーズ 運命のリスボン
監督:ラウール・ルイス
出演:アドリアヌ・ルーシュ マリア・ジュアン・バストゥシュほか
製作年:2010年
製作国:フランス ポルトガル