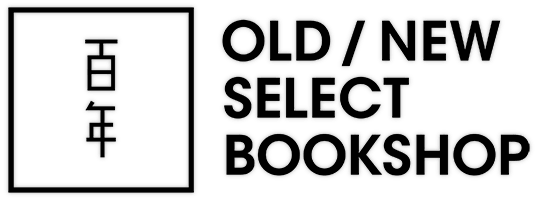本からはじまるいろいろなこと 1
■「オススメ」するのではないブックガイド
辻本:今日は『〈建築〉としてのブックガイド』の刊行記念としてトークイベントをさせて頂きます。「本からはじまるいろんなこと」というお題で、この本の話をしつつ、出版の現状であったりとか、本を出すということについて、いろいろと話していきたいと思います。
藤原:仲俣暁生さんは以前「季刊・本とコンピュータ」という雑誌の編集長をされていて、今は「マガジン航」というウェブサイトを運営されたり、最近では電子書籍等にもいち早く反応されてますね。個人的に仲俣さんと僕は「路字」というフリーペーパーを一緒に作ったりといったご縁もあるんですけど、今日はフリーランスの編集者としてずっと活動されている仲俣さんの目にこのブックガイドがどう映るのかをお聞きしたくてお呼びしました。
仲俣:今日はこの本を、思い切り褒めるつもりで来ました(笑)。
藤原:(笑)そして百年店主の樽本樹廣さん。このブックガイドにも執筆者のひとりとして参加いただきました。元々樽本さんは大手の新刊書店に勤めたのちに、独立して百年を立ち上げられた。言うなればインディペンデントな町の本屋さんですよね。その店主兼オーナーという立場から、出版や本についてあれこれお聞きしたいと思います。じゃあまず簡単にこのブックガイドの説明をしましょうか。
辻本:簡単に言いますとこの本は「〈建築〉としての」とタイトルにあるので一見すると建築の本のように思われがちですが、そうではなくて、一冊のブックガイドを建築物に見立てていて、「玄関」「トイレ」「書斎」「浴室」など、いろいろなパートがあるんですね。要するに各部屋の機能やイメージから選書してもらい、書評エッセイを書いていただくというのがこの本の基本コンセプトになってます。「門」というパートから始まって「屋上」で終わるんですけど、それ以外に実は表紙カバーの裏側にも「船着き場」というパートがあって対談が収録されたりしています。
藤原:それぞれのパートに一人づつ、「リビング」ならこの人っぽいなーとか、「テラス」だったらこの人面白そうだ、とか指名・配置していったんです。それで樽本さんには「玄関」を依頼しました。
仲俣:樽本さんの原稿を最初に読んだんですが、伸び伸びと肩の力が抜けてて、すごくいい原稿でしたね。
樽本:「玄関からイメージするものを書いてください」と言われて僕なりに自由に考えたんですね。「玄関」って、入り口であり出口である場所だなあと。そこでできるだけ今まで持っていた考え方や知識を一旦横に置いて、軽くなって入っていけるような、そして出ていく時にはできるだけ外の世界でも対応できるような本を選んでみました。……結局ブックガイドって言っても、僕自身、誰かがオススメしたからって別に読まないので、それよりはエッセイのような形であったり、その人がその本を読んで何を経験したのか、どんなふうに血肉化させたのかを知りたいと思って。
辻本:いわゆるオススメっていう感じではやってないですよね。これはもう本全体を通してですけど。
藤原:執筆者のみなさんには、読者の人に対する「オススメ!」みたいな感じでは書かないでくださいってお願いしました。僕は昔、書評雑誌を出している出版社に勤めていたんですけど、メインの読者層はやっぱりSFなりミステリーなり何らかのジャンルにある程度慣れ親しんでいる人たちですよね。そういう経験値の高い手練れの読者に対しては、確かに目利きによる「オススメ」のブックガイドはすごく役に立つし、楽しいものでもあります。でもじゃあ今のもっと若い人の感覚として、そもそもジャンルの枠組みで本を読むのだろうか?とかいった疑問もあって、今回あらためてガイドブックを作るにあたっては別の切り口を考えてみようと。それは例えば樽本さんが今話してくださったみたいに、選者の文章に血肉化されていくことを通して本を紹介する、といったやり方ですね。
仲俣:なるほどね。このブックガイドには、まだ自分の単著を出していないような新人、特に若い方たちの原稿がたくさん掲載されてますよね。それでまず言いたいのは、なんで執筆者として僕に声をかけてくれなかったんだ!、と(笑)。今日ここに並んでいる他の3人に比べると僕はひと回り年上なんですけど、こんな面白いことやるなら、仲間ハズレにしてほしくなかったなあ(笑)。……それともう1つ思うのは、こういう本だったら、「インディペンデントでやればいいじゃん」と思う人もいるかもしれないけど、僕はそう思わないんですよ。僕が出版の仕事をはじめたのは20歳のときなんですが、その当時、つまり80年代前半って、案外こういう本がたくさん商業出版の出版社からで出ていたんですよね。たぶん全共闘崩れとかそういう人たちがやっていたんだと思いますが、例えば北宋社とか冬樹社といった出版社から、若い書き手(当時はまだ無名に近かった橋本治とか)が楽しそうに本を出していた。そういう本を読んで、自分でも出版の仕事をしてみたいと思った。そういう視点から見るとこの本の佇まいはすごく懐かしい。それで、「ああ、昔はこんな感じの本がいっぱいあったのに、今は出にくくなっちゃったのはなぜなんだろう?」と思ったんですね。
■「強い編集」/「弱い編集」
仲俣:ブックガイドっていうのは、今までたくさんの出版社が本や雑誌として出しているけど、正直に言うと、僕はその手の本がほとんどがダメなんですよ。編集者が普通に考えるブックガイドは、だいたい「〜のための」ガイドになると思うんです。ための、というのは、目的だったり想定読者のことだけど、とにかく目的がある。今回の『〈建築〉としてのブックガイド』の何がミソかっていうと、「~のための」じゃなくて、「〜としての」っていうところでしょう。つまり目的ではなくて、形式・方法論だけがある、という不思議な本なんですよね。
藤原くんはこのところ、たくさん演劇を観てる様子だけど、その影響があるのかもしれない。というのも、この本は「建築」を意識していると同時に、「演劇」にも似ていると思うんです。編者の藤原くんと辻本くんの二人が、演劇でいうところの「演出家」になって、「〈建築〉としてのブックガイド」という芝居をやっているような感じ。そのお芝居のなかでは、「玄関」とか「子供部屋」とかが「役」に当たって、それぞれの役をいろいろな書き手に与えてる、という感じに読めるんですよね。選者=役者に指名された人は、「あなたは玄関だから」と言われても、必ずしも玄関が登場する本を選ぶわけではなくて、「玄関」という場所から、何らかのイメージを引っ張り出そうとしてる。そこに選者なりの、その場所と自分の人生との、いろいろな関係性や身体感覚が出てくる。そこが面白いと思ったんです。それは、あるジャンルの専門家が本をオススメするというガイドとは全然違った、すごく個人的なものだけど、ではそれがアマチュアのものにすぎないかというと、僕はそうは思わないんですよね。むしろ、そういうものこそが本当の「書評」なんじゃないか、とも思うんです。
去年、編者ということでクレジットしてもらった『編集進化論』(フィルムアート社)という本の前書きに、これからは読者自身がメディアを編集できてしまう時代だ、ということを書いたんですけど、そのときにプロの編集者がやらなくちゃいけないことは何なのか、ということを考えた。それは多分、読者によっても編集が可能なような「場」を作ることじゃないかな、と。強いコンセプトでガチガチに固めるんじゃなくて、そこで何かが起きるような場所(紙であれ、デジタルであれ)を作ること。僕はそれを、試みに「弱い編集」と呼んでいるんです。あらかじめテーマがあって読者を強く縛る「強い編集」に比べると、方法論だけ提示して後は自由にやってくださいっていう感じなんですが、そういう「弱い編集」って、実はすごく難しいんですね。そういう、思いがけないマジックが起きるような「場」を作るという点でも、この『〈建築〉としてのブックガイド』という本はよく出来ていると思いました。
辻本:書き手の困惑だったり、探りながら書いている様子が伝わってくるところが結構あって、そこも含めて面白いかなって思いました(笑)。
藤原: 演劇との絡みで言うと、昨日たまたま「こまばアゴラ映画祭」というのに呼ばれて「演技と演出を考える」という座談会の司会をやったんですね。そこで松井周さん(劇団サンプル主宰)が仰っていたのは、例えば俳優に「犬なのか、女の死体なのか、わからないのをやってくれ」と稽古で無茶振りすると。でもそれを役者は困惑しながらもやってみるし、そこから面白いものが生まれてくる可能性があるんですよね。そういった演劇的な面白さが、このブックガイドを作る過程にもあった気がします。
辻本:ちょっと無責任に聞こえるかもですけど、とにかく投げてみて、結果何が返ってくるかわからないというのも面白かったんですよね。
仲俣:「編集する」、あるいは「原稿を依頼する」っていうのは、本当はそういうことなんだよね。原稿の頼まれ方には、「原稿発注」と「執筆依頼」の2種類があるんですよ(笑)。つまり、「発注」された原稿を書くのが「ライター」で、「執筆依頼」をされるのが「作家」なんですね。ライターへの発注は、あらかじめレイアウトが確定している場合が多くて、文字数も何文字かける何文字と決まってる。多くの場合、テーマに沿うように中身を合わせる必要もある。ようするに「下請け」の仕事です。もちろんライターを貶めるつもりはないし、一時期は出版界も景気がよかったから、ライター的な仕事をする物書きがものすごく増えた。でも今は、「発注」自体が減っている。そういう原稿を待っていて書いてるだけじゃ、もう食べていけなくなった。だから、ライターも本当の意味での「作家」にならなきゃいけない時期にきていると思うんです。あらゆる原稿は「発注」されるんじゃなくて、著者と編集者が一緒にものを作っていく、「原稿依頼」という原点に戻ること。この本は懐かしいのと同時に、これこそがベーシックな本のあり方なのかもしれない、という気持ちにさせてくれたんです。
■もうひとつの2000年代、DTPの浸透
藤原:ところで今日最初にみなさんにお配りしたテキストは、仲俣さんが今朝作ってきてくれたものなんですけど(http://www.scribd.com/doc/49571044/guidebooks-for-losing-ways)、この「思いついたから今朝作ってきた」っていうスピード感覚はすごく重要なポイントな気がするんですね。
仲俣:これはインデザインで今朝ささっとつくって、「スクリブド」というネット上の文書共有サイトにアップロードしてあるので、誰でもダウンロードできます。
藤原 :僕もフリーの編集者になって経済的に苦しい時期がかなり続いたけど、なんとかだましだまし生きてこられたのって、DTP(デスクトップパブリッシング)のスキルがあったのが大きいんですよ。出版社時代に見よう見まねでインデザイン(組み版ソフト)の使い方を覚えたんですけど、それが後々助けになりました。数時間あればそれなりのペーパーを作れちゃう。そうやってミニコミを作って手売りして、雨露をしのぐ、みたいなことをやってた時期もあります。まあ今も相変わらずそんな感じですけど(笑)。
辻本:路上詩人みたいですね(笑)。
藤原:このトークが始まる前に仲俣さんが「ゼロ年代ではない2000年代があった」と仰ってたんですけど、それって僕の解釈だと、バブルが崩壊して、90年代の暗い時代が過ぎて、ノストラダムスの大予言もはずれて世界が終わることもなく、まあ9.11みたいなことは起こりながらも、窮屈な世界が続いてきたと。その間にインターネットが登場して、ある種の部分が強烈に可視化されて、ゲーム的な言論のシーンやコンテクストにのっとったサブカルチャーの空気が醸成されてきたと思うんですけど、それは僕にとっては少し窮屈な感じがしました。21世紀に入って最初の10年も終わったことだし、そろそろその空気とは違うことをやってみたいというのはありました。
仲俣:1995年に阪神淡路大震災やオウムの事件があって、それからは暗い時代で……という若い人たちの世代認識と僕の感覚はちょっと違って、むしろ90年代はとても楽しい時代だったんですね。同世代の佐々木敦くんや原雅明くんがHEADZという編集と音楽の事務所を立ち上げたのもその頃で、横目でみていていいなと思っていた。バブル経済が崩壊して、「シティロード」という、僕のつとめていた雑誌がつぶれたとき、まわりにいた音楽ライターやフリーの編集者が、自分でレーベルを立ち上げたり、クラブでDJをやったりして、原稿を書いたり雑誌をつくるだけじゃなく、リスナーに直接、音楽を聴かせる場所を作ろうとしたんですよ。音楽の世界はインターネットとの繋がりも早かったし。でも、いまはMac一台にDTPソフトさえあれば、本や雑誌も簡単にできてしまうちゃうんですよね。まず、それをやることが楽しい、ということが先にあって、それによって食べていくことについては、それぞれのやり方でなんとかやっていく。誰だって出版以外の仕事をしたり、どうしても足りないときはお金も借りたりしてるはず(笑)。でも、出版社だって本業以外に収益のあがるビジネスを他にやってるところはたくさんあるし、それがないところは銀行からお金を借りて、自転車操業で回してる。出版だけでは食えないという意味では、個人も会社も同じなんですよね。
そう思うと、「ゼロ年代はなんだか暗い時代だった」的な認識とは別の、「もうひとつの00年代」があったんじゃないか、その時代に僕らがやってきたことの中に、この先の時代にも繋がるヒントがいっぱいあるんじゃないかな、って。例えば佐々木敦くんが主宰して、藤原くんや辻本くんも編集に携わってる雑誌「エクス・ポ」もそうだと思うけど、現場で思いついたことをすぐ形にしていくことで、なにか繋がっていくものがあるはずなんです。
■2000年代におけるインディペンデントな場の登場
仲俣:「場」ということでいうと、この百年を含む、新しいタイプの古本屋さんのブームも、2000年代における見過ごせない流れの1つだと思います。紙媒体をつくることが簡単になっただけでなく、それを売ったり、こういうイベントをやったりすることができる場所が増えた。インターネットによって、そういうインディペンデントな場と作り手や読者が結びついた。そう考えると、「00年代」も、あんまり食えなかったことを除けば、楽しいことしかなかった10年間だったのかもしれない、とも思うんです(笑)。
藤原:食えなかった、というのはそれはそれで問題ですけど(笑)。でもこういうペーパーを売ってくれる場所があったのも大きいですよね。中野のタコシェや新宿の模索舎のようにずっとミニコミ文化を支えてきた老舗のお店に加えて、百年みたいな新しいインディペンデントのお店が出来て、そこに自分が作ったメディアを置いてもらえるっていうのは、新しくメディアを作ろうとする人のモチベーションにもなり、具体的な助けにもなったと思います。
樽本:たしかにうちに持ち込んでくれる方も同年代が多くて、考え方も近くて、話し合ってるうちに、じゃあ販売しようってなるケースが多いですね。逆にそこで考え方が違うと、モノが良くてもダメ。ただ作っておしまいっていうのは違うと思うんです。やっぱりお店なので、1冊の本を置くスペースに対して責任が持てるのかどうか。それはひいては本を作ったことに対しての責任だとも思うんで。例えば辻本さんの「生活考察」だって、この本を置くためのスペース分はやっぱりお店に対して利益を出してくれないと、辻本さんだって僕だって生活していかなきゃならないから。そういうことをわかった人とやりとりをしたい。大手の書店にいた頃は、そういう関係の持ち方ができないことがイヤだったんですね。委託だしそっちはリスクないからこんだけ置いてよとか、この本は売れるから置きなさいよとか。そういうんじゃなくて、こちらも面白がって、お客さんにも自信を持って勧められるものを置きたいと。
あと、うちは「セレクトブックショップ」ということにしてるんですけど、実はセレクトってことをあんまりしてない。まあ、良いものと悪いものはあるから多少するけれど、ガチガチに専門店化することなくやっていくのがいいと思ってますね。
辻本:それ、さっき話に出た「弱い編集」というのとも繋がりそうですね。
藤原:「セレクトブックショップは店主の好み全開の世界でけしからん」みたいな批判が一時期強くありましたけど、百年はそういったタイプのお店とはちょっと違いますね。
樽本:僕もそこは批判した人間のひとりです(笑)。買う本がないから。確かに洒落てはいるんだけど、身になる本がない。専門店化しちゃって敷居が高くなっている。そうではなくて、町の本屋がもともと好きだし、そういう店でありたいなと。
辻本:専門店化しないとはいえ、お店を始めるにあたり、樽本さんなりのコンセプトはあったと思うんですけど、だんだん今みたいな品揃えになってきたって感じですか?
樽本:基本的には古本屋なんで、お客さんが売ってくれる本で店が成り立っている。だから、何があるかとか買い取るまでわからないんですよ。うちは本を売り買いする場所なんで、本を買うだけじゃなくて、売ってほしい。その繰り返しが古本屋なんで。
藤原:樽本さんは商売人っていう感覚もすごくある気がします。例えば下北沢の「ほん吉」の加勢さんもかなりの商売人だなって思うんですけど。
樽本:そこらへんが必要になってきたかなーと思っていて。やっぱり自分たちで何かしていかないと、社会は何もしてくれないし、もちろん会社員として出来ることもたくさんあるだろうけど、たまたま僕はそういう場所にいなかったから、自分でやるという選択をした。図太さも持たなければならないんだろうな、ということは20代半ばを過ぎた頃からひしひしと感じてきましたね。
仲俣:ここではいろいろ、自主的なイベントをやってますよね。編集者ではないけれど、こうしたお店をやりながら、誰かと誰かを出会わせる作業を樽本さんはしてると思うんです。
樽本:僕が興味を持った人をお呼びするので、その人にアクセスすると、お客さんも新しく来て、そこからお店がひろがっていくのがイベントをやるいちばんの魅力ですね。そこで生まれる熱であったり、人であったり。イベントをやるってことはだから、最初からのこの店のコンセプトであり、戦略でした。
藤原:イベントのタイトルにいつも「百年と〜」って付けられる意図は?
樽本:それは、石子順造というマンガや美術の批評の人が、「と」っていうのは8の字を描くように人と人を仲人させるようなものだと言ってて。だから「and」じゃないんですよね。「with」に近いかもしれません。
(第2弾へつづく)