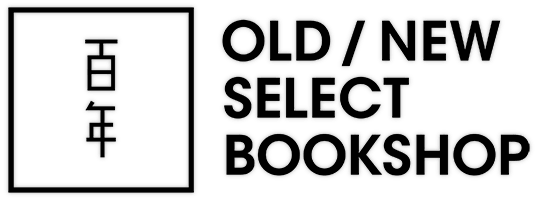海炭市叙景レビュー

冬には厚い雲が立ちこめて、陽の降りそそぐことの少ない北の街が舞台となっているからだろう、劇中、映しだされる建物の多くが、少しでもたくさんのひかりを屋内に取りこもうと、おおきく窓をとっていたり、戸を磨りガラスにしたりしている。日が陰り、外の気温が下がればさがるほど、ストーブで暖まった家のなかとの温度差は広がるから、そうなると自然、両者を隔てる窓は結露して、その向こうにあるものの輪郭をぼやかしてしまう。キャメラの据えられたこちら側と、雪の舞うあちら側が、あくまで異なる場所だということを透明なガラス板があらためて気づかせてくれる。
佐藤泰志が遺した“ひとつの”短編集、『海炭市叙景』のなかから、いくつかのエピソードをつなぎ合わせて作ったというこの映画は、あるいは、そんな一枚の窓ガラスを媒介として、凍てつく街に暮らす人々の揺れ動くさまを描いた物語だといえるのかもしれない。
たとえば冒頭、真っ暗なスクリーンにサイレンの音が鳴り響いて、次の瞬間には、白く曇った窓が映しだされる。外ではいったい何が起きているのだろうとこちらが思ったのも束の間、ちいさな子どもの手がガラスの露を払って、その滲んだ合間から、冬の景色が垣間見える。まもなく、この街の中心的な役割を果たしている港湾で起こった、ただならぬ事故は、窓のこちら側である小学校の教室にも及んできて、授業中、連絡を受けた教師によって呼び出されたふたりの兄妹が、寒々しい廊下で顔を合わせ、手をつないで歩きはじめることで、物語は動きだしていく。
事故から数年のときを経て、妹がせわしない仕草で兄を起こすときにも、質素なたたずまいの家の窓が、一日の始まりを示すものとして画面に映しだされる。カーテンが開けられ、白く曇った窓ガラスが顔をのぞかせることで、その日、その場所が、どれだけ寒いかが観ているこちら側に伝えられる。ふたりはその後、支度を済ませて、あわただしく造船所に向かうのだけれど、そこで待ち構えているのは、彼らの意思を蔑ろにした、無残な決定でしかない。造船所が人員削減のため、従業員の解雇を進めており、彼らもまた、その処遇に従わざるを得ないからだ。
市から住居の立ち退きをせまられている老婆の場合もまた、一日の仕事は引き戸の磨りガラス越しに始まっている。まだ陽がのぼりきっていない時間帯に動きだした彼女は、早朝、玄関で明かりをつけたのち、ようやく外に出てきて――ガラス戸のこちら側に姿を見せて――日銭を稼ぐため、公設の市場に手作りした漬け物を売りにいく。
その後の物語では、車や路面電車が頻繁に登場する。若くして父親からガス屋の社長業を引き継ぐことになった男が、苛立ちを募らせながらも移動に用いるのは、白い軽トラックであるし、中年の男性が、数年来、顔を合わせていなかった息子をたまたま見かけるのは、路面電車を操縦しているときだ。雪道を走る自動車や運行する路面電車のフロントガラスが白く曇ることはないけれど、彼らがみずからの不安や問題に気づいたり、思い悩んだりしたりするのは、いつでも窓のこちら側で、そんなとき外ではたいてい、寒風吹きすさぶ、と表現したくなるような情景が広がっている。
函館をモデルにしているという「海炭市」はつまり、着の身着のまま気軽に戸外にピクニックに行けるような土地とは異なる、寒さの厳しい地方都市だということができるのだけれど、だからというべきか、この映画に登場する誰もが、外出するときにはそれなりの装備を求められる冬の日常さながら、抱えこんだ不満や悲しみ、それに落胆を、容易に洩らしたりはしない。それぞれが窓の内側に身をひそめて、事態が好転するのをひたすら待ち続けてみるものの、解決の糸口は見えてこないばかりか、状況はよりいっそう困難になっていく。思い煩った末、追い立てられるようにして窓の外に出たところで、そこに待ち受けているのは決着という言葉からは程遠いものなのだから、観ているこちらが息を呑むのも、ある意味、当然といえるだろう。
初日の出を見るため、ロープウェイで山に向かった兄妹も、飼い猫を探して家の外に出ていった老婆も、水商売に身をやつした妻を連れ戻そうと店に向かった夫も、そしてまた、従業員の代わりにガスボンベの交換に出かけた男や、郷里に帰ってきたにもかかわらず、実家には行かずに客引きの誘いに応じてスナックに足を運んだ男性も、行き着く先にあるのは、淡く、やるせない結果でしかない。
それにしても、この映画に出てくる人たちの寄る辺なさは何なのだろう。
書きなぐったような文字でスクリーンにタイトルが映しだされる直前、「わたしたちは、あの場所に戻るのだ」というモノローグが流れるけれど、戻る場所さえ定かではない私たちが、すぐさまこれを自分のこととして当て嵌めるのは、少し違う気もする。それには、地域性といった問題のみならず、連続する複数の物語が、途中でわずかに交差しながらも、行き場を失ったまま結末を迎えるという構成が多いに関係している気がするのだけれど、果たして、そんなことはないだろうか。
ともあれ、二時間半という長さのあるこの映画を、少しも飽きることなく観続けることができたのは、北の地方都市の日常を虚心に捉えようとした、作り手の姿勢によるのだろう。
ロープウェイの発着所で、山頂から遊歩道をつたって下りてくるはずの兄を待つ妹の背後には、ガラスの壁を隔てて、寒々しい冬の景色が広がっている。
海炭市叙景
出演:谷村美月、竹原ピストル、加瀬 亮、三浦誠己、山中 崇、南 果歩、小林 薫、
製作:菅原和博、前田絋孝、張江 肇 企画:菅原和博、「海炭市叙景」製作実行委員会
プロデューサー:越川道夫、星野秀樹 ラインプロデューサー:野村邦彦
原作:佐藤泰志(クレイン刊「佐藤泰志作品集」所収/小学館文庫刊)
監督:熊切和嘉 脚本:宇治田隆史 音楽:ジム・オルーク 撮影:近藤龍人 照明:藤井 勇
録音:吉田憲義 美術:山本直輝 スタイリスト:小里幸子 編集:堀善介 助監督:野尻克己
[2010年 / 日本映画 / カラー / 35mm / DTSステレオ / 152分]
© 2010佐藤泰志/『海炭市叙景』製作委員会
12月18日より渋谷ユーロスペースにて上映中 他全国順次公開
公式サイト