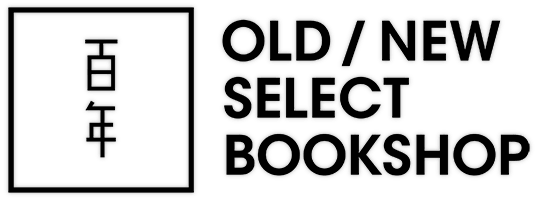高橋マナミさんインタビュー
大学を卒業するとき、自分が何になりたいとかなかった
高橋●大学を卒業するとなったとき、友達は皆、航空会社に入りたいとか、新聞記者になりたいとか、目指すものがあって就職活動をしていましたが、私はなりたいものがありませんでした。でも、就活はしなきゃいけない。なんとか内定をもらって社会人になりましたが、「夢ってどうやったら見つかるんだろう」という悩みが入社3年目くらいでさらに大きくなって。
―― 仕事はつまらなかった?
高橋●いえ、社内外の人との出会いだったり、それなりにいろいろ任せてもらったり、やりがいはあったんですけど、一年を通して残業しない日がないような働き方をしていました。自分の要領が悪かったせいもあったと思いますが、ここにいるまま結婚して、子供を産むとなったら、私には続けていけないだろうな、と思って。
―― 戻れるという雰囲気はあった?
高橋●もちろん制度的には戻れるには戻れますが、産休・育休で戻ってきて、本当に私はここで働けるんだろうか、と考えて。一度辞めてそのうちに再就職といっても、資格も持ってないし、なにか手に職をと思ったんです。でも、夢の見つけ方がわからず悩んでいたくらいですから、代わりの何かなんてすぐには思いつかなくて。それでも、どうしようかなぁとあれこれ考え続けていたら、急に「写真」という選択肢が目の前に現れまして。
―― 写真の学校には通ったんですか?
高橋●会社員4年目の6月頃に写真という選択肢が出てきたのですが、「夢が見つかった」と思いたくて無理やり夢をつくろうとしているだけかもしれないと、自分に対して半信半疑だったので、まずは写真教室に通ってみて、はまるようだったら、会社を辞めて写真の世界を目指す方向に突き進もうと思って。慎重なのか思い切ったことしてるのかよくわかりませんが(笑)。幸い写真が楽しくて、「よし、このまま!」と会社を辞めることを決めて年度いっぱい3月まで働きました。そして4月から2年間、学校に通いました。
―― どこに通っていたんですか?
高橋●東京ビジュアルアーツです。だから写真を始めたのは26歳。遅いですよ。本当にぎりぎりだったかなと思って。専門学校に入ったのが28歳になる年だったので。29歳で卒業して、30歳の時にはアシスタントをしていました。
―― 撮りたいものっていうのはあったんですか?
高橋●それはですね、人によっては不純な動機と笑うかもしれないですが、「夢ってどうやったら見つかるんだろう」っていう「夢」を考えようとしたきっかけのひとつに、私、ミュージシャンのゆずと何かものづくりをしたいというのがあって。
―― すごいですね(笑)。
高橋●ちょうど夢を模索していたときに、彼らがデビュー10周年で、『月刊カドカワ』だったりいろんな雑誌が特集を組んでいて、そのカドカワで、ゆずとそれまで一緒に仕事をしてきた人たちの彼らに対するコメントが出ていて。そこで良くないコメントがあるわけないのはわかっているんだけれど、心底「彼らと仕事をしてよかった」ということがヒシヒシと伝わるような言葉がいろんな人から寄せられていて、私も仕事をしたいと思いました。すいません、唐突な話のようですけど(笑)。堂々と向き合って一緒にものづくりをしたいと思ったのですが、じゃあなんだろう、って。私は絵は下手だし、粘土とか彫刻もできないし。基本的に不器用だから。
―― 笑。
高橋●音響とかも私には違うだろうな・・・と思って、なんぞやなんぞやと考えていたときに、『WHAT’s IN XP』という音楽誌のムックが発売されて、中平卓馬さん・富永よしえさん・吉永マサユキさんの3人がそれぞれゆずを撮りおろすという1冊で。
―― そんな企画があったんですね。
高橋●ああ、こういう向き合い方があるんだとハッとして、それが「写真」と思った決め手だったと思います。
―― 対等に向き合いたい。撮りたいとは違う?
高橋●もしかしたら、雑誌でポートレイトを撮るとか、今もまったく可能性がない状況にいるわけではないかもしれませんが・・・。
―― まだ実現してない?
高橋●してない(笑)。早く会って撮りたいという気持ちと、一方で、何かをつくりあげるために満を持したい気もして、不要な葛藤を勝手にしています(笑)。
―― そこまでの思いだと逆に会わないほうがよさそうな・・・。
高橋●夢であり、モチベーションであり、目標かなと思います。写真で自分に何ができるのかまったくわからずに写真を始めたので、経験をするにつれ、やれることややりたいことはいろいろと変化してきていますが、その夢は最初から今も変わりません。
―― そうなんですね。学校では、人を撮るような課題も多かったのでは?
高橋●そうですね。ポートレイトで仕事をしていきたいと思って学校に入りましたから、すぐにでも取り組みたかったのですが、最初はなかなかうまいこといかずに・・・。ここに河川敷の写真があるんですけど。これは写真を始めてからずっとやっていることで、ポートレイトとは全然違うものですが、これが自分としてはすごく好きで、気持ちよくって。いまだにライフワークみたいにやっています。ほかにも、実家の記録とかしていました。当時築50年くらい経っていて、かと言って素敵な古民家というわけでもなく、ただ古いだけだったんですが、大きい地震とかきたら壊れちゃうんだろうなと漠然と思っていて。それじゃあ記録をしておかないとと、ちゃんと記録をするようなことを始めたりとか。そのときはまだ震災前でのんきな気持ちでの取り組みだったようにも思いますが、その後の震災で、家は結果的に外壁の一部や風呂場のタイルが剥がれるくらいで済みましたが、ちょうど震災のあとすぐに実家を建て替えて、今はもうあの家は存在しません。生まれてからずっと、あんなに長いこと暮らしていた場所なのに、やっぱり細部の記憶は曖昧なんですよね。あの壁の模様はどんなだったとか。写真で記録をしていて、結果やっておいてよかったというのがありました。そんなふうに、全然ポートレイトとはかけ離れたことばかりをやっていました。




高橋●2年生になってポートレイト専攻に進みましたが、それでもなかなか人を撮ることにうまく取り組めずにいました。夏前くらいに卒業制作のテーマを2つ決めないといけなくて、ひとつはこの河川敷の作品にしたんですけど、もうひとつ、専攻のほうのポートレイト作品として取り組んだのが、この制服の作品「later and ago」でした。




―― じゃあこれは学生の頃に撮ったものなんですね。
高橋●そうです。それまでは、授業で目の前にいる友人をそのまま撮ることしかできずにいましたが、初めて自分で状況を選択しながら“ザ・ポートレート”を撮るっていう。遅いですけど、やっときっかけにたどり着きました。
―― でも、これただのポートレイトじゃないですよね。
高橋●制服というものに嫉妬というか憧れみたいなものがあって。制服を着た高校生を街で見かけると、大人に片足突っ込んでいるのだけれど決して大人ではなくて、でも子どもでもない、どこか脆いような、独特の感じを受けるんですけど。だけどちょっと想像して、この子たちと私服で会ったらそういう感じはしないんじゃないかと思ったんですね。制服がつくる魔法みたいなものって何だろうと思って。制服ってずるいなぁって思ったんですよね(笑)。じゃあ、もう高校生じゃない人に制服を着せたらどうなるのかしらと、単純な興味から始まりました。
―― みんな自分たちが高校時代に着ていた制服?
高橋●自分の制服を持っていた人には自前でお願いしたんですけど、残念ながら、けっこうみんな捨ててしまっていて。
―― 男なんかは特にそうですね。
高橋●そうですね。だから、ない人にはこっちで用意して貸しました。
―― 被写体の人たちはどうやって選んだんですか?
高橋●知り合いか、知り合いの知り合いです。
―― この被写体が高校生かそうでないかの判断は難しいところですね。男なんかこういう高校生いなくはないなぁって。でもなんか、違和感は感じますね、やっぱり。特に女性が多いですね。でも制服着てるしな・・・って。
高橋●ギャグにはしたくなかったので、そうした判断迷うようなぎりぎりのところにいそうな人たちを選んだつもりではあります。そこは気をつけました。ギャグにもなりかねない不自然な設定で真面目にポートレイトを撮るっていう。これがポートレイトにちゃんと取り組んだ初めての作品でしたが、そうしたらやっていてすごくおもしろくて。ああ、いいなポートレイト、って思いました。
―― 数があるからいいですよね。一人をいろんなシチュエーションで撮るとギャグのところに落ちがちだけど、比較対象があることで浮かび上がってくるものがある。そこがすごくおもしろいなぁと思った。みんないい顔してる。
高橋●そう、いい顔するんです、結果的に。みんな、まず普通に私服で待ち合わせをして、駅前のドトールのトイレとかで制服に着替えてもらって。そのトイレから出てきたときは本当にモジモジ。それこそ、犯罪じゃないかって顔して出てくる(笑)。そこをスタートに一緒に散歩しながら世間話とかをして。あ、ここがいいなと思った場所で止まってもらって撮るみたいな感じでやったんですけど、歩き始めて5分も経つと、みんな最初の戸惑いやためらいは忘れて、普通になってるんです。決して、高校生に戻った気分でいてほしいというようなことはお願いしてないし、なりきってほしくもなかった。彼らのほとんどの人の高校生当時を私は知らないから、当時との比較はできないんだけれど、それでもやっぱり私が魔法と思って嫉妬した「制服」というものに包まれちゃってるなぁって感じがして。向き合っていて、こっちも不思議な気持ちでしたね。楽しかったし、ポートレイトが好きだと思った。それまでは、ゆずっていう夢のために無理やりポートレイトをやりたいと思い込もうとしてるんじゃないかと、夢を見つけたときと同じく、またも自分に対して半信半疑なところがあったんですけど、そうじゃなくて本当にやりたいって思いました、これで。
―― どうでした評判は?
高橋●これに、アシスタントを卒業してから少し撮り足したものをまとめて、キヤノンの写真新世紀に応募して、佳作をいただきました。初めてのポートレイト作品で、自分としては好きなんだけれど、果たして撮影時の思い入れを抜いて客観的に見れているのか不安もあったので、そういった一定の評価をしてもらえたというのはホッとしました。